導入
こんにちは、DeNA の IT 基盤部第一グループでインフラエンジニアとして働いている大田 雄土です。
私は 2024 年 8 月から現在まで、キャリアで初めてメンター業務を担当しています。きっかけは、新卒エンジニアの方が私たちのチームに配属されたことでした。フレッシュな新メンバーを迎え、どのようにチームに馴染んでもらい、成長を支援していくか—その役割を担うことになったのです。
約半年間のメンタリング経験を通じて、多くの学びや、また失敗がありました。この記事では、メンティーが主体的に考え行動できるようになることを目指す上で、私が経験した試行錯誤のプロセス、特に初期の失敗から得た教訓と、そこから見えてきた「信頼関係の土台作り」から「主体性を引き出すための具体的な働きかけ」へという段階的なアプローチについて、共有したいと思います。
これからメンターを担当する方、もしくは現在メンターとして奮闘されている方々にとって、少しでも参考になる点があれば幸いです。また、現在メンティーとして成長途上にある方々にとっても、メンターや周囲がどのような意図で関わっているのかを知る、一つの手がかりになるかもしれません。
ただし、ここで紹介する内容は、あくまで私個人の経験に基づく一事例・一意見です。組織やチームの状況、メンバーの特性によって最適な方法は異なりますので、その点はご留意いただければと思います。
第 1 章:全ての始まりは「安心して頼れる信頼関係」という土台から
メンティーが主体的に考え行動できるようになることを目指す上で、私が自身の経験から最初に痛感したのは、技術や知識を教えること以上に、まず全ての土台となる『安心して頼れる信頼関係』を築くことが何よりも重要だということでした。
信頼関係がなければ、どんな指導も逆効果になりうる
【原則】心理的安全性の重要性(なぜ挑戦・発言できる環境が必要か)
まず、「安心して挑戦・発言できる環境」、言い換えれば、心理的な安全が確保された状態は、なぜメンティーの成長に不可欠なのでしょうか?
それは、人が新しいことを学んだり、難しい課題に挑戦したりする際には、失敗や間違いがつきものだからです。分からないことを「分からない」と素直に言えたり、失敗を恐れずに「まずやってみる」と行動できたり、自分の考えや懸念を率直に表明できたりする環境があって初めて、人は効果的に学習し、能力を最大限に発揮できるようになります。逆に、萎縮してしまったり、質問をためらったりする環境では、成長の機会そのものが失われてしまいます。
【失敗談】良かれと思った「問いかけ」が「問い詰め」になっていた頃
このようなことは一般論として誰でも頷くことですが、実際にそれを実現するのは容易ではありません。頭では理解していたつもりでしたが、メンターになりたての私は、この「土台作り」の重要性を本当の意味で理解できていませんでした。
むしろ、「自分で考える力をつけてもらいたい」という気持ちが先行し、良かれと思って「思考を促すアプローチ」を多用してしまったのです。
例えば、メンティーからある設定ファイルの変更方法について質問を受けた際、すぐに答えを示すのではなく、「そもそもこの設定は何のためにあると思う?」「なぜその変更が必要だと考えたの?」といった問いかけから入りました。メンティー自身に深く考えてもらうことを意図した行動でした。
しかし、当時のメンティーはまだ前提知識や経験も浅く、私の問いかけに戸惑い、答えることができませんでした。実際のところ私がやっていたのは「考えを促す」ことではなく、「問い詰められている感覚」を与える行為でした。
その結果、次第に、メンティーからの質問の頻度は明らかに減っていきました。「聞いてもすぐには教えてもらえない」「的外れなことを言って逆質問を受けるかもしれない」と感じさせてしまい、結果的にメンティーを遠慮させ、孤立を深めてしまったのです。
私自身も、メンティーの状況が見えにくくなり、「ちゃんと進んでいるのだろうか」と不安になり、マイクロマネジメントに陥りかけるという、負のスパイラルにハマっていました。これは非常に危険な状態でした。
【教訓】手法の前に、まず「安心感」と「信頼」
この苦い経験から、私は大きな間違いを犯していたことに気づかされました。
どんなに効果的と言われる育成手法や指導法も、メンティーとの間に「この人は自分の味方だ」「困ったときには助けてくれる」「安心して頼れる」という基本的な信頼関係と安心感がなければ、全く機能しない。それどころか、今回のように逆効果にすらなり得るのだ、と。
技術的な指導や、主体的な成長を促すような高度な働きかけの前に、まず、安心して失敗でき、頼れる存在としての関係性を築くこと。この「土台」作りこそが、メンタリングにおける何よりも譲れない最優先事項なのだと、身をもって学びました。
安心と信頼の土台をどう築いたか:具体的な 3 つのアプローチ
その大きな失敗と学びを経て、私はメンタリングのアプローチを大きく見直しました。ここからは、信頼関係と安心感を築くために、具体的に意識して取り組んだことをいくつか紹介します。
実践 ①:期待値のズレをなくし、不要なプレッシャーを取り除く
【課題認識】
特にメンタリング初期に気になったのが、メンティーの過度な遠慮や謙遜でした。テキストコミュニケーションツールとして使っている Slack で「🙇」の絵文字が頻繁に出てきたり、質問すること自体をためらったりする様子が見られました。また「早く一人前になって、たくさんの仕事をこなさないとチームに迷惑をかける」というようなプレッシャーを感じているように見える場面もありました。
【意図/目的】
私とマネージャーは、メンティーの様子を観察する中で、この「期待されている(と思い込んでいる)こと」と「チームが実際に求めていること」のギャップに気づきました。このギャップが、メンティーの不要な不安や焦りを生み、結果としてパフォーマンスを下げていると考え、この認識のズレを解消し、安心して業務に取り組めるようにすることが大切だと考えました。
【具体的な行動】
そこで、まず私とマネージャーで「今のチーム状況では、焦って多くのタスクをこなすよりも、一つのタスクにじっくり時間をかけて品質を高める方が価値がある」といったチームとしての方針をすり合わせました。その上で、チームとしての期待として、メンティーとの 1on1 で、「必要以上に丁寧に振る舞う必要はないこと」「たくさんのタスクを早くこなすことより、一つのタスクを高品質に完了させることを重視していること」「速度よりもクオリティを優先してほしいこと」などを、具体的かつ明確な言葉で伝えました。
【結果/効果】
この働きかけの結果、過度な遠慮が減り、より本質的で建設的な質問が増えました。また不要な焦りから解放され、タスクに落ち着いて取り組めるようになったようにも見受けられ、成果物の質も向上しました。期待値を丁寧に伝えることが、メンティーの不安を取り除き、よりオープンで信頼に基づいた関係を作るための一助となったのです。
実践 ②:「いつでも、どんなことでも聞ける」雰囲気を作る
【意図/目的】
先の失敗から、とにかく「いつでも」「どんなことでも」安心して聞ける環境を作ることが重要だと痛感していました。
【具体的な行動】
- 「チームに来たばかりで背景知識や文脈を知らないのだから、既存メンバーにとっては当たり前でも、わからないことがあるのは仕方ない場面もある」ということを伝え、「困ったらすぐに聞いてください」「他に詰まっているところはないですか?」といった声かけを 1on1 などにおいて繰り返し行いました。
- 質問を受けた際には、以前の失敗を踏まえ、「メンティーは思いつく最善を尽くした上でこの質問をしてくれているのだ」と受け止め、丁寧に対応することを心がけました。
- また、意識的に自分自身の失敗談や「これ、私も詳しくないんですよね」といった弱みを見せることも、メンティーが「自分だけじゃないんだ」と感じ、心理的なハードルを下げるのに役立ったように思います。
- チームミーティングでメンティーに話を振ったり、メンティーが聞きづらそうにしていることを察して「〇〇について、私も気になっていたんですが…」と代理で質問したりすることも、チーム内での発言しやすさをサポートする上で効果的でした。
【結果/効果】
こうした地道な積み重ねによって、メンティーは疑問や不安を一人で抱え込まず、率直に、そして早期に相談してくれるようになりました。
実践 ③:失敗を許容し、「やってみる」を後押しする姿勢
【意図/目的】
成長には挑戦が不可欠ですが、挑戦には失敗がつきものです。ミスを過度に恐れることなく、安心して「やってみる」という行動を促したいと考えました。
【具体的な行動】
- メンティーが新しいタスクに取り組む際などに、「もし他の人から何か言われたら、メンターの僕がそのやり方で賛成している、と言っていいから、安心してやってみて」といった声かけをしました。これは、心理的なセーフティネットを用意し、萎縮せずに行動できるよう背中を押す意図でした。
- 実際にミスが起きた時も、個人を責めるのではなく、「なぜそうなったのか」を冷静に分析し、「〇〇さんらしくないですね、最近忙しかったり疲れたりしていましたか?次はどうすれば防げるか一緒に考えましょう」と、失敗を成長の糧として捉える姿勢を意識的に示しました。
【結果/効果】
次第に、メンティーは失敗を過度に恐れることなく、新しいタスクや少し難しい課題に対しても「まずはやってみます」と前向きに挑戦する姿勢を見せるように順調に成長してくれたと感じています。
このように、失敗からの学びを活かし、期待値の調整、質問しやすい雰囲気作り、失敗を許容する姿勢といった具体的なアプローチを通して、少しずつですが、メンティーとの間に『安心して頼れる信頼関係』という、その後の成長に不可欠な『土台』を築いていくことができていったと感じています。これは、メンティーがチームで活躍していくための重要な第一歩です。
第 2 章:主体性を引き出す「学び」と「実践」のサイクルを回す
土台の上で効果的な成長を促すために
第 1 章で築いた「安心して頼れる信頼関係」という土台は、メンティーが新しいことに挑戦したり、難しい問題に取り組んだりする上でのセーフティネットとなります。この安全な環境の中で、メンティーがより効果的に学び、応用力を身につけ、主体性を発揮していくためには、どのような支援をすればよいのか、私は考え始めました。
マネージャーと育成方針ややり方について議論したり、自身のエンジニアとしての成長経験を振り返ったりする中で、効果的なスキル習得や能力向上には、「① 理論や考え方を自分のものにする(インプット)」と「② それを実際の場面で試してみる(アウトプット)」というサイクルを意識的に回すことが良いという考えに至りました。この「学びと実践のサイクル」をメンタリングの中心に据えることが、メンティーの主体性をさらに引き出す上で効果的だと考えたのです。
この章では、そのために私が具体的に取り組んだ 2 つの取り組みについてお話しします。
ステップ 1:「答え」ではなく「考え方」を伝える
主体性を育むサイクルの最初のステップは、「考え方」をメンティーの中にインストールすることだと考えました。個別のタスクの「答え」や手順だけを教えても、状況が変われば応用が利きません。重要なのは、「なぜそうするのか」「どのような思考プロセスで問題に取り組むのか」という、再現性のある「考え方」そのものを理解してもらうことです。
なぜ「考え方」を伝えることが重要なのか?
特に、私たちインフラエンジニアの業務では、定型作業だけでなく、予期せぬトラブルへの対応や、状況に応じた最適な構成の検討など、応用力が求められる場面が多くあります。このような状況で自律的に判断し行動するためには、表面的な知識だけでなく、その背景にある原則や思考プロセスを習得していることが不可欠です。
これを身につけることで、メンティーは未知の問題に直面したときにも、学んだ型を応用して自分なりに解決の糸口を見つけ出すことができるようになります。これが、主体的な課題解決能力の基盤となると考えました。
実践例:アラート対応から学ぶ「インフラエンジニアの思考プロセス」
実践したこと:
例えば、インフラ業務で重要なアラート対応において、単に「このアラートが出たらこう対応する」という手順を教えるだけでなく、その背景にある「思考プロセス」を言語化して共有することを意識しました。
思考プロセス(例:1.事象把握、2.影響範囲と緊急度評価、3.一次対応(復旧措置)優先、4.原因調査、5.恒久対応検討)を伝え、なぜその順序や判断が重要なのか(例:ユーザー影響を最小限にするため、など)という理由もセットで説明しました。
しかし、一方的に説明するだけではなかなか身につきません。そこで特に効果的だったのが、メンティーが実際に対応を経験した後の 1on1 での振り返りです。この場で、実際の行動と理想的な思考プロセスを照らし合わせながら対話することで、学びを深めてもらおうと考えました。
例えば、あるアラート対応の後、次のような対話を行いました。
【翌日の1on1ミーティングにて💬】
メンター💁: 「昨日のアラート対応、お疲れ様でした。少し振り返りをしてみましょうか。
アラートが来たとき、まず何をしましたか?」
メンティー🙍♂️: 「ログを確認して、エラーの原因を調査しようとしました。
ただ、調査に時間がかかってしまいました...」
メンター🙍: 「なるほど。原因調査に向かうのは自然な反応ですね。インフラの
アラート対応では少し違う順序が効果的な場合もあります。」
メンティー💁♂️: 「他にどういうアプローチがあるんでしょうか?」
メンター🙍: 「まずはサービスへの影響度を確認するという方法です。サービスが
停止しているなら、原因がわからなくても、まず『復旧』を優先します。フェイルオーバー
するとか、バックアップからインスタンスを作り直すとか。原因究明は安全確保の後でも対応できます。」
メンティー🙍♂️: 「確かに、ユーザーへの影響を最小限にすることが最優先ですね。
原因調査に集中するあまり、サービス復旧が遅れるリスクもありますね。」
メンター💁: 「そうですね。他に何か気づいたことはありますか?」
メンティー🙍♂️: 「一人で問題に取り組んでいたので、解決に時間がかかりました。
チームに状況を共有すべきだったかもしれません。」
メンター🙆: 「その気づきは重要です。特に初めて対応するケースや、影響度が大きい
アラートの場合は、早めにチームに共有する方法もあります。
『助けて』と言うのは弱さではなく、むしろプロフェッショナルな対応だと思います。」
メンティー🙋♂️: 「チームの力を借りた方がより早く効果的に解決できますね。」
メンター💁: 「そうですね。次回似たようなアラートが来たら、どんなアプローチを
考えていますか?」
メンティー🙆♂️: 「まずサービス影響を確認して、必要なら復旧対応を優先します。
また、状況に応じてチームにも早めに共有するようにします。」
メンター🕺: 「素晴らしいですね。そのアプローチで対応できると効果的だと思います。」このような対話を通じて、一方的に教えるのではなく、メンティー自身の経験と結びつけながら「思考プロセス」を理解し、内面化していくことをサポートしました。
得られた結果:
こうした振り返りの積み重ねにより、メンティーは徐々にアラート対応における判断基準や優先順位の付け方を自身のものにしていきました。結果として、初めて見る種類のアラートに対しても、学んだ考え方を応用し、以前よりも落ち着いて、自律的に判断・行動できる場面が着実に増えていきました。
(これは、第 1 章で築いた信頼関係の土台があったからこそ、メンティーが自分の思考や行動を安心して開示でき、このような率直で深い対話が可能になったのだと確信しています。)
ステップ 2:身につけた考え方を「実践」する機会を創り、定着させる
「考え方」をインストールするだけでは、まだ十分ではありません。学んだことを本当に自分のものにし、自信を持って使えるようになるためには、実際に自律的に課題に取り組み、成功体験を積む「実践」の機会が不可欠です。これが、主体性を育むサイクルの次のステップです。
なぜ「任せる」ことが成長に繋がるのか?
この機会を多く持ってもらうために、私は、メンティーの成長段階に合わせて適切なレベルの裁量を与え、「任せてみる」ことが大切だと考えました。
自分で考え、判断し、行動した結果としてタスクを完遂できた、あるいは困難を乗り越えられた、という成功体験は、「自分はやれるんだ」という自己効力感を高めます。また、タスクを「任される」ことで、当事者意識(オーナーシップ)が芽生え、「やらされている」のではなく「自分が主体となって進めている」という感覚が、さらなるモチベーションに繋がります。
もちろん、任せる際には、メンターによる適切なサポートや見守りが必要です。しかし、主体性を育む上では、この「任せる勇気」と「見守る姿勢」が極めて重要になると考えました。
実践例:成長段階に合わせた「委任レベル」の見極め
どうやって「任せる」か? - 参考にした考え方:
では、具体的にどのように「任せる」範囲やレベルを判断すればよいでしょうか? これを考える上で、私は Konifar さんのブログ記事『“提案"のレベルを上げる』で紹介されている「提案レベル」の考え方が非常に参考になりました。
レベル 0: 「どうすればいいですか」
レベル 1: 「どれにしましょうか」
レベル 2: 「自分はこれがいいと思います」
レベル 3: 「これでいいですか」
このレベル分けは、メンティーがどの程度自律的に考え、判断できるかの目安として捉えることができます。
実践したこと:
私は、メンティーとの日々のコミュニケーションや依頼するタスクの内容を通じて、「今の彼は、この件についてどのレベルで考え、提案できそうか?」を意識的に観察するようにしました。そして、そのレベル感に合わせて、私の関与度合いや任せる裁量を調整していきました。
- レベル 0 ~ 1 に近い段階では、まだ未知の領域でわからないことが多い状態なので、丁寧に説明し、選択肢を示し、一緒に考える時間を多く取ります。具体的な指示や、こまめな進捗確認も行います。
- レベル 2 に近い段階が見えてきたら、まずは「あなたはどうしたい?どう考える?」と問いかけ、本人の意見を引き出すことを優先します。その上で、必要に応じてアドバイスや別の視点を提供します。タスクの進め方についても、ある程度の裁量を任せてみます。
- レベル 3 に近い段階であれば、基本的に本人の判断を尊重し、最終的な確認や承認、困ったときの相談役というスタンスで見守ります。「この件は〇〇さんにお任せしますね」と明確に伝え、オーナーシップを促します。
時には、メンティーの成長を感じ取った時に、「少し難しいかな?」と感じるタスクであっても、勇気を持って『任せてみる』ことも重要でした。例えば、以前は必ず一緒に行っていた定例作業の主担当を任せたり、少し複雑な調査依頼を「まずは自分で進め方を考えてやってみて、壁にぶつかったら相談してください」と促したりしました。もちろん、丸投げではなく、困ったときにはいつでもサポートする姿勢は大切です。
得られた結果:
任されたタスクを一つひとつ乗り越える経験を通じて、メンティーは着実に自信をつけていきました。「以前はメンターに頼っていたこの作業が、今は一人でできるようになった」という実感は、何よりの成長の証であり、次の挑戦への意欲に繋がります。
自分で考え、判断し、行動する経験を積むことで、多くの場面で「どうすればいいですか(レベル 0)」から「自分はこう考えますが、どうでしょうか(レベル 2 ~ 3)」へと、提案のレベルも着実に向上していきました。
メンティーが困難を乗り越え、タスクを完遂した際には、「〇〇さん、あの難しいタスク、最後まで自分でやりきって本当に素晴らしかったですね!△△ の判断、すごく良かったと思いますよ!」といった具体的なフィードバックを意識的に伝えることで、それが成功体験を強化し、さらなる成長意欲を引き出す良いサイクルが生まれることも実感しました。
【補足】ただし、「任せる」ことの難しさも痛感
一方で、この『成長段階の見極め』と『適切な任せ方(委任レベルの調整)』は、口で言うほど簡単ではなく、今でも非常に難しいと感じています。常に試行錯誤の連続です。
メンター側の「もうこれくらいできるはずだ」という期待が先行しすぎると、メンティーにとっては過度なプレッシャーとなり、自信を失わせる逆効果にもなりかねません。また、得意な領域と不得意な領域、あるいはタスクの種類によって、メンティーが見せる「レベル」は常に変動します。
そのため、画一的な見方をするのではなく、常に個々のタスクや状況、そして本人の意欲やコンディションに注意を払い、時には手厚くサポートするなど、柔軟に対応することの重要性も痛感しています。それでも、主体的な成長を促す上では、この「見極めて任せる」という挑戦を続ける価値は大きいと信じています。
結論:主体的な成長を支えるメンタリングで本当に大切だと感じたこと
経験から得た学び:メンタリングは相互成長のプロセス
ここまで、私がメンターとして歩んできた約半年間の、決して平坦ではなかった試行錯誤の道のりをお話ししてきました。特に、初期の失敗から学んだ「信頼関係」という土台の重要性、そしてその土台の上で「主体性」を育むための「学びと実践のサイクル」という考え方について、具体的な経験を交えてお伝えしました。
この経験を通して痛感したのは、メンタリングは決して一方通行ではない、ということです。メンティーの成長を間近で支援する中で、私自身も多くのことを学ばせてもらいました。メンティーからの鋭い質問や新鮮な視点にハッとさせられることも多く、教える立場/教わる立場という固定的な関係ではなく、エンジニアとして互いに刺激し合い、共に成長していくことの大切さを強く感じています。
核心メッセージ:主体的な成長は「土台」と「サイクル」から生まれる
改めて、私の経験から得た核心的なメッセージをまとめると、メンティーが主体的に考え行動できるようになるためには、以下の二段階のアプローチが極めて重要だと考えます。
- まず、何よりも先に『安心して頼れる信頼関係』という強固な土台を築くこと。 これがなければ、どんな働きかけも効果を発揮しません。
- その土台の上で、『考え方を学ぶ』と『それを実践する』というサイクルを回すこと。 これにより、学びが定着し、自信と応用力が育まれます。
最後に:メンターとして、これからも
メンターの役割は時に難しく、悩むことも多いと思います。私自身、今も日々試行錯誤の真っ最中です。しかし、失敗は決して無駄ではなく、必ず次への貴重な学びにつながります。この記事が、皆さんのメンタリング活動や育成への取り組みにおいて、何か一つでもヒントとなり、試行錯誤を恐れずに前進する一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
私自身、この経験で得た学びを胸に、今後もより良いメンタリングを模索し続け、チームメンバー一人ひとりが安心して挑戦し、主体的に成長できる、そんな組織づくりに貢献していきたいと考えています。






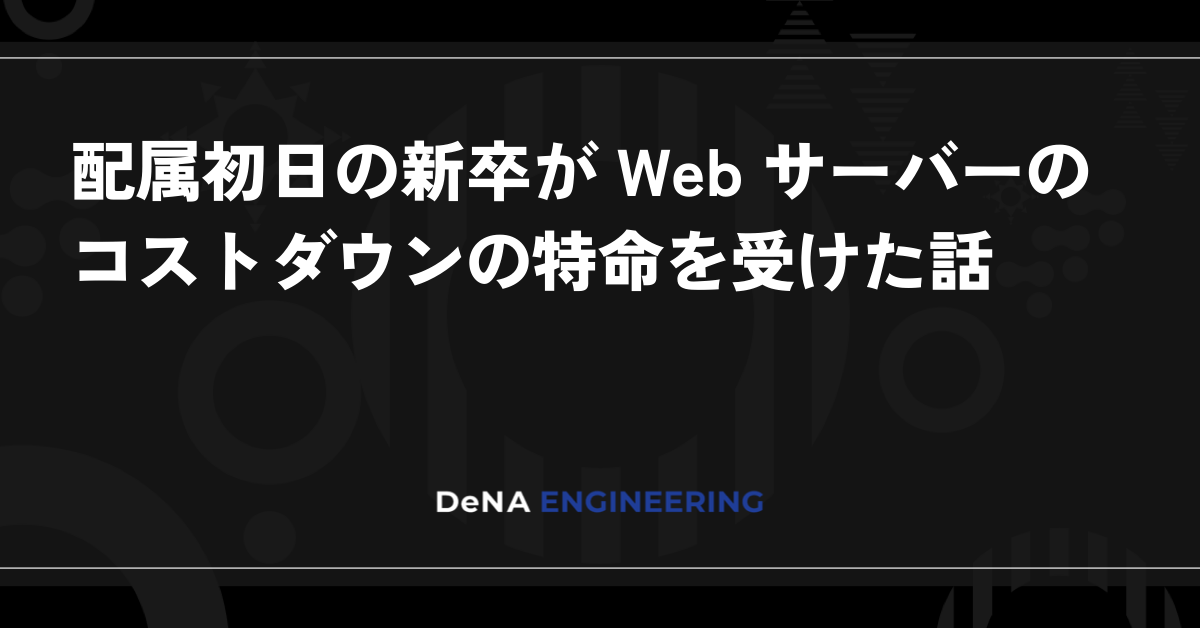
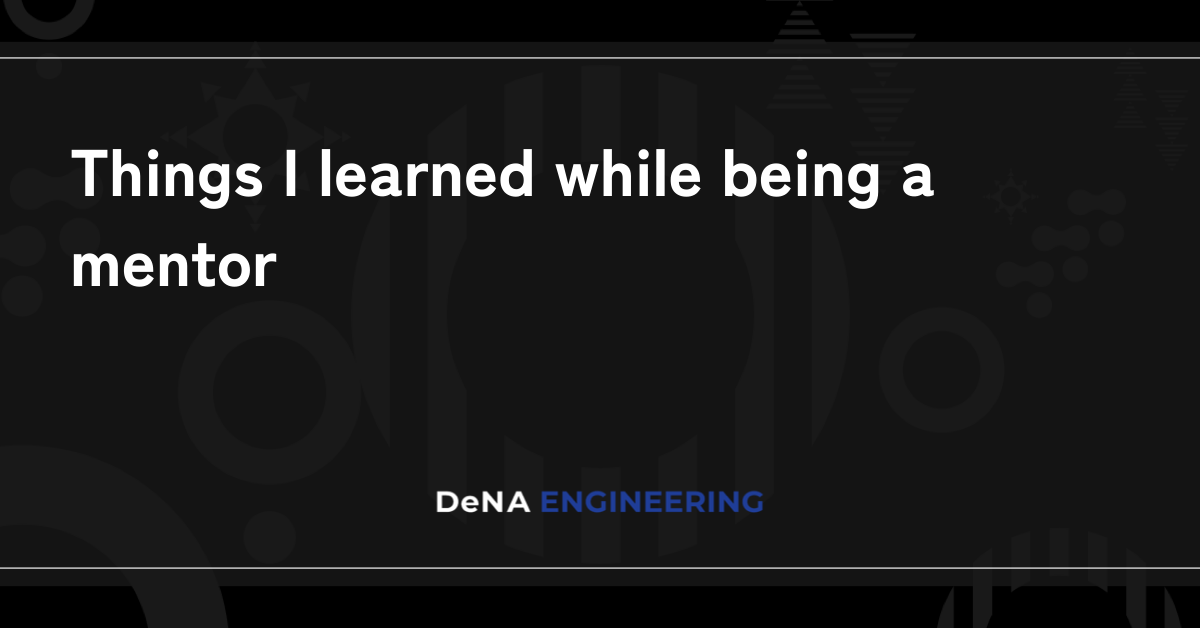
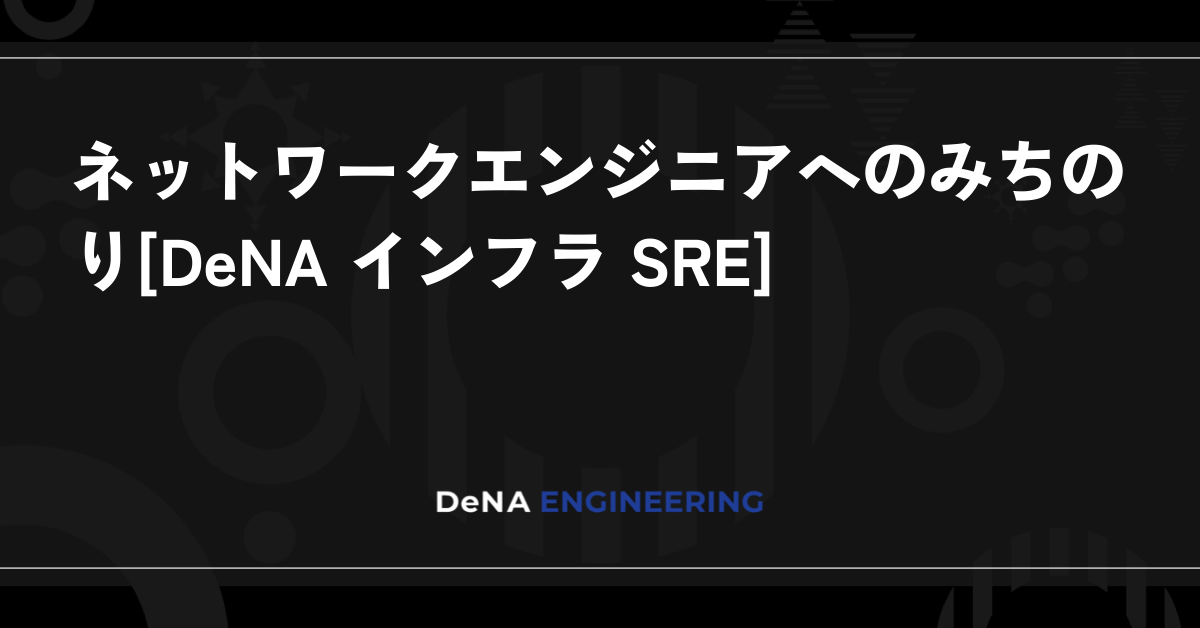

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。