はじめに
こんにちは! ライブコミュニティ事業本部 Pococha 事業部の Takuya Shinjo と Hiroshi Onodera です。
この記事では開発案件にAIコードエディター「Cursor」をどのように導入したのか、導入によって開発者体験がどのように変化したのかを紹介します。
導入のきっかけと目的
私たちPayment Solutionチームは、決済機能の開発、運用業務を行っているチームです。また、PocochaにおけるAI駆動開発を推進する役割も担っています。 この役割を担うことになった背景には、CursorやClineなどのAIコードエディターを早期から積極的に導入しメンバー全員がAI活用に前向きだったこと、AIツールを実際に使って得た学びを積極的にフィードバックしていたこと、サーバーエンジニアがメインの体制でAIツール適用に取り組みやすい環境が整っていたことがあります。 そんな中、ちょうど全社でAIコードエディター「Cursor」の利用が可能になったタイミングと、「コイン購入における不正決済対策機能の改修」プロジェクトの開始が重なりました。 そこで私たちは、この案件を「Cursorを全面的に活用すると、開発スピードや品質、そして開発者体験はどう変わるのか?」を検証するための絶好の機会と捉え、実践することにしました。
AIコードエディター ✕ ペアプロ
今回のプロジェクトでは、具体的な実装はCursorに指示し、人間は設計やレビューに集中する、というスタイルを取りました。
2名体制で、以下のようなサイクルで開発を進めていきました:
- 午前: Cursorを使いながら人間同士でペアプロ
- 午後: 各自がCursorを利用しつつソロで開発
- 翌日: 前日にソロで実装したコードを再びペアでレビュー
Cursorがもたらした「開発者体験」の変化
このプロジェクトでは、開発工数を当初の見積もりから半分以下にまで大幅に削減でき、リリース後に重大なバグが出ないなど品質も担保することができました。 しかし、私たちが今回の検証を通してもっとも共有したいのは 「開発者体験」の変化 でした。
1. AIコードエディターはペアプロ相手
AIコードエディターが単なるツールではなく「ペアプロ相手」という実感でした。
私達はいわゆる「プロンプトの工夫」はそこまで意識せずに、人間と対話する際と同じようなやり取りを心がけ実装を進めました。
「こういう目的で、こういう設計にしたい」と全体像を共有して認識を合わせ、その上で具体的な実装を依頼する。そして、出てきた結果に対してフィードバックを行い、修正してもらう。 この一連のサイクルが極めてスムーズなのは、Cursorが単にコードを提案するだけでなく、エディター上で直接ファイルの作成や修正ができるおかげです。
2. 認知負荷の軽減と、本質的な作業への集中
AIコードエディターを利用することで「認知負荷が明確に下がった」という点は、利用者メンバー全員の共通意見でした。 とくに、既存コードの仕様を把握する際に解説させることで、理解にかかるコストを大幅に削減できたと感じます。 その結果、私たちはより本質的な「どう作るか」という課題に集中する「頭を使う余裕ができた」と感じています。
3. 客観的な視点が生んだ「セルフレビュー」の質の向上
AIが生成したコードを常にレビューする、というプロセスは、私たちに 「第三者としての客観的な視点」 を自然と養ってくれたと感じています。 ときに自分自身が書いたコードに些細な誤りやケアレスミスを見過ごしてしまうことがあります。 しかし今回は、AIコードエディターが作成した"他人"のコードを見ることで、一歩引いてコードを確認できました。
4. 想定外の手戻りにも対応できる安心感
前述の通り今回の開発は開発工数を当初の見積もりから半分以下に削減でき、計画を前倒しで進めることができました。 これは単に「早く終わる」以上の価値をもたらしてくれていると感じます。 具体的には「着手してみて想定外のことがあっても、スピードで巻き返せる」「手戻りが起きても、素早く気づき修正できる」といった、プロジェクト進行上のリスクを減らせるという大きなメリットがあると感じています。
導入において認識した課題
実装担当者以外のレビュアーからは「AIが書いたとは分からない自然なコードで、重要な指摘事項は見当たらなかった」というポジティブなフィードバックもいただきました。 しかしその一方で、AIコードエディターならではの課題も認識しました。 それは、既存コードの暗黙のコンテキストや実装の意図までは読み取れないことです。 私たちがすべてのコンテキストをAIにインプットすることは難しく、修正による影響範囲を考慮すると現時点では修正すべきではない箇所ををリファクタリングしてしまう、ということもあり人間による判断・修正指示が必要でした。 対策として、設計段階でAIコードエディターでの実装範囲を明確にしておくなど、関係者で共通認識を持っておくことが、円滑な開発を進める上で有用、という話があがりました。
現在取り組んでいること
今回の検証を通じて得た知見も活かしつつ、私たちは組織全体でのAI駆動開発をより体系的に推進しています。 設計や実装といった導入済みのプロセスでは効果測定とチューニングを継続しつつ、PRDレビュー、テスト効率化、レビュー自動化など、ソフトウェア開発プロセス全般にAI活用を拡大しているところです。
現在進行している主な取り組みは以下の通りです。
参考記事
各AIツール共通のコンテキスト・ルールセットの整備
現在Cursor、Cline、Claude Code、Junie、Gemini CLIほか、多様なAIコードエディターが次々と登場しています。 これらのツールを効果的に活用するには、それぞれに対してコーディング規約やプロジェクト固有のルールを個別に設定する必要があります。 しかし、AIコードエディター毎の設定の手間に加えて、定義した内容が属人化してしまったり定義した内容がちゃんと効果を発揮しているのかも不明確、といった課題を多くのメンバーが感じています。
そこで私たちは、妥当な定義をツール横断で汎用的なものとして作成し、今後登場する新たなAIツールに対しても活用できる「資産」として整備することで、どのツールでも一貫した品質のアウトプットを得られるようにすることを目指しています。
AIツールの適用範囲拡大
PRDレビューとDesign Doc作成の効率化
要件定義やアーキテクチャ設計フェーズでのAI活用を進めており、PRDのレビュープロセスの改善やDesign Docの作成支援に取り組んでいます。
テスト効率化への適用
QAメンバーと連携し、テスト設計へのAI活用を進めています。
新たなAIコードエディターの利用
- Claude Code
- Gemini CLI
- Junie (JetBrains AI Pro)
レビューツールの試用
- Code Rabbit
- pr-agent
おわりに
私たちは、今回の導入を通じてAIコードエディターを「ただのツール」ではなく「頼れるペアプロ相手」として捉えることができると学びました。 そのポテンシャルを最大限に引き出す鍵は、単にコードを書かせるだけでなく、設計の相談、実装の試行錯誤、そして人間同士のレビューという一連のサイクル全体に、AIコードエディターを本当のパートナーとして参加させることでした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。本記事が、皆様のAI活用推進に少しでも参考になれば幸いです。






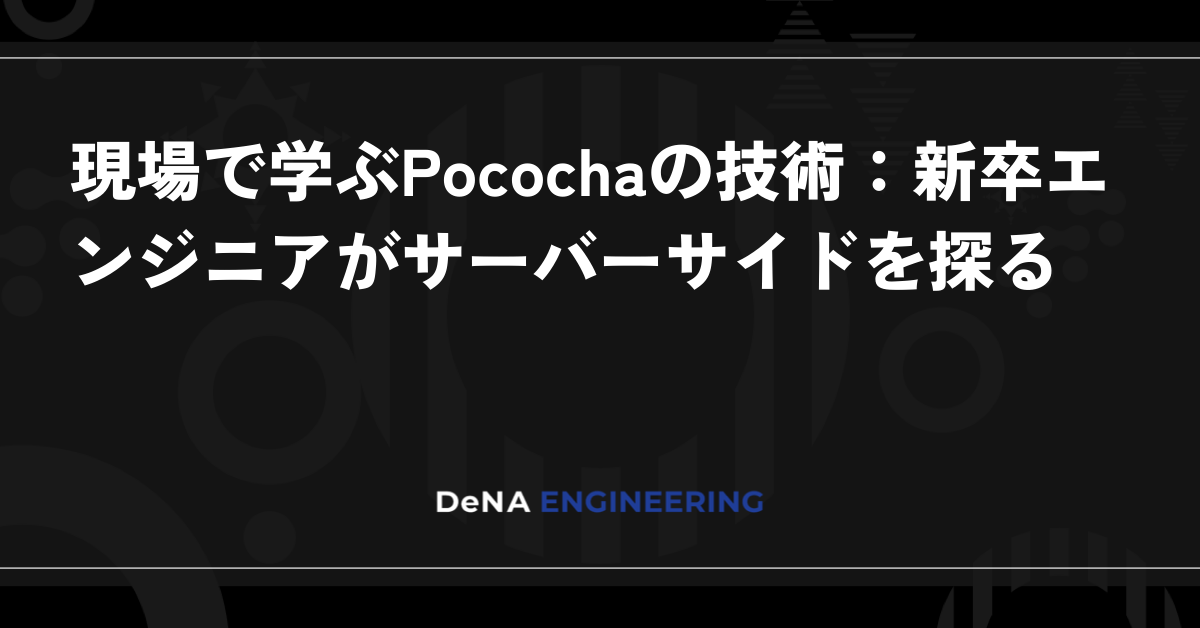
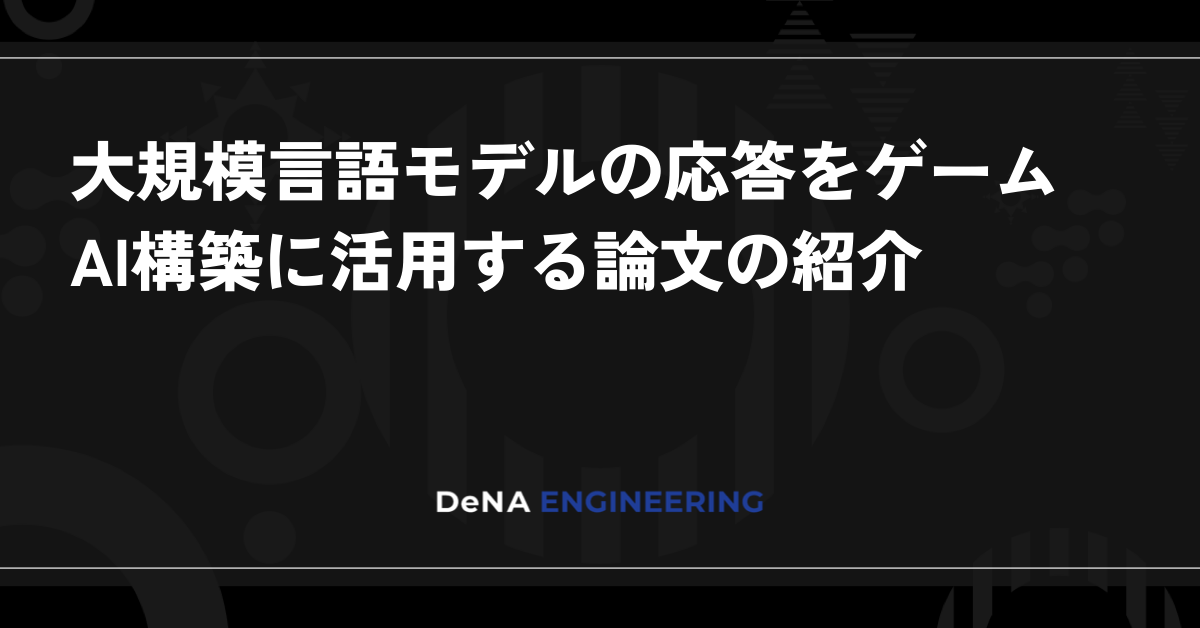
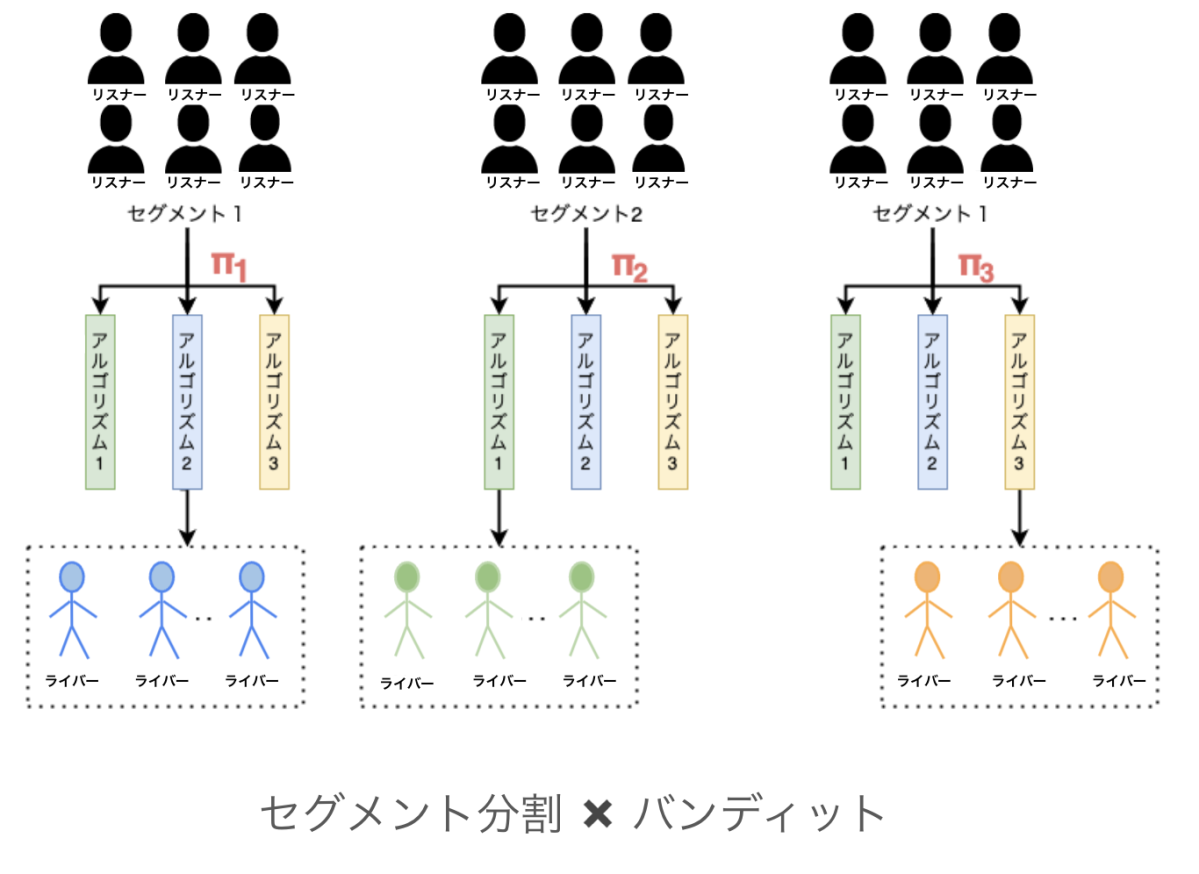

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。