はじめに
社内のAI環境やAIツールの提供をリードしているIT本部が中心となって社内のAI戦略や活用事例、その裏側にあるストーリーを発信する企画「AIジャーニーの足跡」。
今回から始まる第2幕では、IT本部の新卒エンジニアが社内を駆け巡り、ビジネスや開発の現場でどのように AI が活用されているのかをレポートしていきます。今回は、データ分析の最前線で活躍する「アナリティクスチーム」にお話を伺いました。
DeNA の各事業において「参謀」としての役割を担うデータアナリストたち。事業の拡大に伴い、増え続ける分析ニーズに対し、彼らはどのように AI を組み込み、組織を進化させているのでしょうか?
キーワードは 「AIネイティブアナリスト」。
「個人のスキルアップ」よりも「システムの進化」を優先する、その革新的な取り組みの全貌に迫ります。
プロフィール
- 佐々木 亮
- ゲームサービス事業本部分析部 シニアデータアナリスト / 株式会社DeNA AI Link Devin推進部 部長
- 「AIネイティブアナリスト」構想の発案者。ポッドキャスト「となりのデータ分析屋さん」でも知られる、分析組織のキーマン
- 樋富 啓央
- データアナリスト(21新卒)
- AI活用の実装・推進担当。GitHub や GitHub Copilot を用いた分析環境の整備を行い、チームのAI化を牽引する
- 浜岡 凌誠
- データアナリスト(25新卒)
- SQL や開発環境に触れたことがない状態で配属され、今回のAI活用システムの最初のユーザーとして実証実験に参加
- 田邉 優斗(インタビュアー)
- データ基盤部 MLエンジニア(25新卒)
- AI活用事例に興味があり、AIジャーニーの足跡のインタビュアーとして立候補
依頼急増のジレンマ「参謀」であり続けるための決断
田邉: まず、AI導入以前の分析チームはどのような課題を抱えていたのでしょうか?
佐々木: もともと DeNA のアナリストは、単に数字を出すだけの「受託分析」ではなく、事業責任者のパートナーとして企画段階から入り込む 「参謀」スタイルを大切にしてきました。
しかし、サービスが成長したり、あるいは不調で改善が必要な局面になると、どうしても「数字にすがる」場面が増え、分析依頼が急増します。これまでは、リソースが足りなくなると「引き受けられる範囲を狭める」という対症療法しかなく、参謀として深く入り込みたくても、手作業の集計に忙殺されてしまうというジレンマがありました。
田邉: 確かに、事業規模が大きくなればなるほど、その課題は深刻になりそうですね。
樋富: そうですね。私が担当していたような小規模タイトルであれば、「参謀」としての役割が強くなりますが、『 逆転オセロニア 』のような長年続くゲームになると土台ができているため、タスク内容が変わります。 本来アナリストに求められるのは、SQL を叩く作業そのものではなく、「相手がどう進めたいか」「市場はどう動いているか」を踏まえた 戦略的な提案(コミュニケーション) です。そこに時間を使うためには、構造的な変革が必要でした。
「暗黙知」を「形式知」へ。AI活用の方程式
田邉: 実は以前、「AIネイティブアナリスト」という構想があるとお聞きしたのですが、これは具体的にどういうものなのでしょうか?
佐々木: 一言で言うと、 「SQL を書くといった作業は AI に任せ、人間は『考えること』に集中する」 という、新しいアナリストのあり方です。
きっかけは南場さんが「AIオールイン」の文脈で話していた「従来の人員リソースの半分でオペレーションを回す」というビジョンと、SQL 作成などの構造的な作業は AI に任せられるのではないかという仮説でした。
目指したのは、 「AI を使えば使うほど、組織全体が賢くなる」 という好循環を作ることです。
これまでの分析業務の最大の課題は、過去のクエリが「誰でも分かる形」で蓄積されておらず、個人の頭の中にある 「暗黙知」 になっていたことでした。これまでも社内向けの分析ツールなどにデータ自体はありましたが、バージョン管理されておらず「どれが正解か分からない」状態でした。
そこで、この課題を解決し、組織をアップデートするロールとして定義したのが 「AIネイティブアナリスト」 です。
具体的には、まずAI活用によって SQL 作成などの構造的な作業を減らし、浮いたリソースで「事業課題の発見」や「戦略策定」といった本来の価値発揮に集中します。
さらに重要なのが、そうした個人の活動を 「チームの資産」 に変える動きです。
私たちは 「一度やった作業は、次回以降すべて自動化する」 ことを意識しています。作成したクエリを AI が理解できる形として残すことで、次回からは AI がそれを読んで作業をやってくれるようになります。
そして、それらのデータは個人の手元ではなく、チーム全員がアクセスできる場所に蓄積されるようにしました。
そのため、誰か一人が経験したことは、チーム全員の AI の知識として共有されます。そうやって、個人の経験が組織全体の力に変わっていく環境を目指しました。
田邉: 具体的にはどのようなツールや仕組みを導入されたのですか?
樋富: まずは導入ハードルを下げることを意識し、使いやすさとプロジェクト毎のツールの利用制限などを考慮し「GitHub Copilot」を採用しました。そして、分析部専用のGitHubリポジトリを作成し、すべてのクエリやナレッジをそこに集約することにしました。
仕組みはシンプルです。
- 過去の良質なクエリやテーブル情報を GitHub に格納する
- 新しい分析をする際は、GitHub Copilot に 「このリポジトリの◯◯を参考にして」 と指示する
- GitHub Copilot が既存のクエリを参考に、新しいクエリを提案してくれる
さらに、基盤チームと連携して「元のデータを壊さない」などの安全ルールを策定したり、システムプロンプトにあらかじめ「仕様確認の項目」を組み込んだりすることで、GitHub Copilot 側から「この仕様項目を埋めてください」と提案させる形にしました。これにより、誰が使っても一定のクオリティが出るように設計しました。
田邉: ツールや仕組みの導入はスムーズに進んだのでしょうか?
樋富: いえ、実はそこが一番苦労した点かもしれません。 ゲームの分析部には、それまで GitHub を使ったことがないメンバーも大勢いました。「今の業務で精一杯」「AI導入やセットアップの手間が重い」という声もありましたし、なにより「マージとは?」「プッシュとは?」という基礎知識から説明する必要があったんです。
田邉: エンジニアにとっては当たり前でも、アナリストにとっては新しい文化だったんですね。
樋富: そうですね。しかも私は基本リモートワークなので、ただドキュメントを渡すだけでは浸透しません。 「今の分析部ではAI導入のハードルが高いのではないか」という仮説を確認するためにも、いろいろな人に直接話を聞きに行きました。全体会で「今月はこんなことをやりました」と進捗を報告して「AI推進を頑張っているな」と認識してもらったり、個別に困りごとを聞いて回ったり。
佐々木さんとも擦り合わせをする中で感じましたが、やはりリモート環境下であっても、泥臭くコミュニケーションを取り、協力しやすい空気を作っていく。AI導入であっても、最終的に大事なのは 「人間同士のコミュニケーション」 だと痛感しました。
田邉: なるほど。ツールだけでなく、文化やリテラシーの部分から「泥臭く」整えていったからこそ、今の「AIネイティブ」な環境があるわけですね。
VS Code 未経験の新人が、AI と共に「即戦力」へ
田邉: そのシステムの「最初のユーザー」となったのが、新卒の浜岡さんだったわけですね。
浜岡: 実は僕、配属された当初は GitHub はおろか、VS Code (開発ツール)もほぼ触ったことがない状態でした(笑)。
最初は佐々木さんからスプレッドシートでサンプルクエリをもらって作業していたのですが、途中から「やったことを Confluence にまとめて」という指示があり、ある程度溜まった段階で「それを Gemini に読み込ませてみて」という指示に変わり……最終的に GitHub と GitHub Copilot の環境が整ったときには、そこに先輩たちのナレッジが詰まっていました。
樋富さんが用意してくれたドキュメントを見ながら進めたら、SQL 未経験の僕でも分析業務が回せるようになったんです。
田邉: それはすごい変化ですね!
佐々木: 実は、彼ら新人の存在が非常に大きかったんです。 ベテランだけでやると、どうしても「言わなくても分かる」という暗黙知で進んでしまいます。でも、未経験の浜岡くんが「これはどういう意味ですか?」と質問してくれることで、今まで言語化されていなかった手順を明文化(ドキュメント化)するきっかけになりました。
人間がやるべき整理を行ったら、結果として業務をAI化する際の最大のハードルである 「暗黙知の壁」 を超えることができました。
浜岡: 最初は「AI のためにドキュメントを書く」という作業に半信半疑でしたが、実際に AI から的確な回答が返ってきたとき、「ああ、こういうことか!」とすべてが腹落ちしました。
樋富: 浜岡君の変化として一番感じたのは、プロンプトの精度向上です。最初は AI に対しても荒い依頼をしていたのが、徐々に精度が上がり、AI への指示(プロンプト)の精度が上がるにつれて、不思議と人間に対する依頼やコミュニケーションの精度も上がったと感じています。
「個人の努力」に頼らない。組織としての新たなスタンス
田邉: この取り組みを通じて、アナリストに求められるスキルやマインドセットも変わってきそうですね。
浜岡: 正直に言うと、僕は「自分でゼロからクエリを書く力」を鍛えようとはあまり思っていません。目的はあくまで「意思決定に役立つ分析」をすること。AI を使って早く正確にできるなら、自分のコーディング能力向上は二の次でいいと割り切っています。もちろん勉強はしていますが、マネージャー陣もそのスタンスを認めてくれています。
佐々木: ここはチームでも議論した重要なポイントです。 エラーが出たときに、これまでは「個人の勉強不足」として処理しがちでした。でも、「個人の勉強」で解決しても、効率化されるのはその人だけなんです。
それよりも、AI が間違えないようにドキュメントを整備したり、レビュープロセスを変えたりすることに時間を使った方が、組織全体の資産になります。「最後は個人の努力でなんとかする」という精神論を断ち切り、システムで解決するアプローチへ舵を切りました。
樋富: 今後はAI活用の「パーソナライズ」も進めていきたいですね。メンバーの熟練度に合わせて AI のサポート内容が変わるなど、個々に合わせた環境が整えば、精神論的な学習コストはさらに下がっていくはずです。
田邉: 非常に合理的で DeNA らしい取り組みだと感じました。本日はありがとうございました!
編集後記
「AI導入」というと、最新のツールをどう使うかに目が行きがちですが、彼らの取り組みの本質は 「暗黙知の形式知化」 と 「組織文化の変革」 にありました。
「勉強して覚える」という従来の当たり前を疑い、AI を活用しながら、システムそのものを賢く育てていく。その結果、新人が即戦力になり、ベテランはより本質的な「参謀」業務に集中できる。 AI時代の組織作りにおける、一つの解がここにあるように感じました。
「AIジャーニーの足跡」では、今後も DeNA 社内のAI活用のリアルな現場をお届けしていきます。








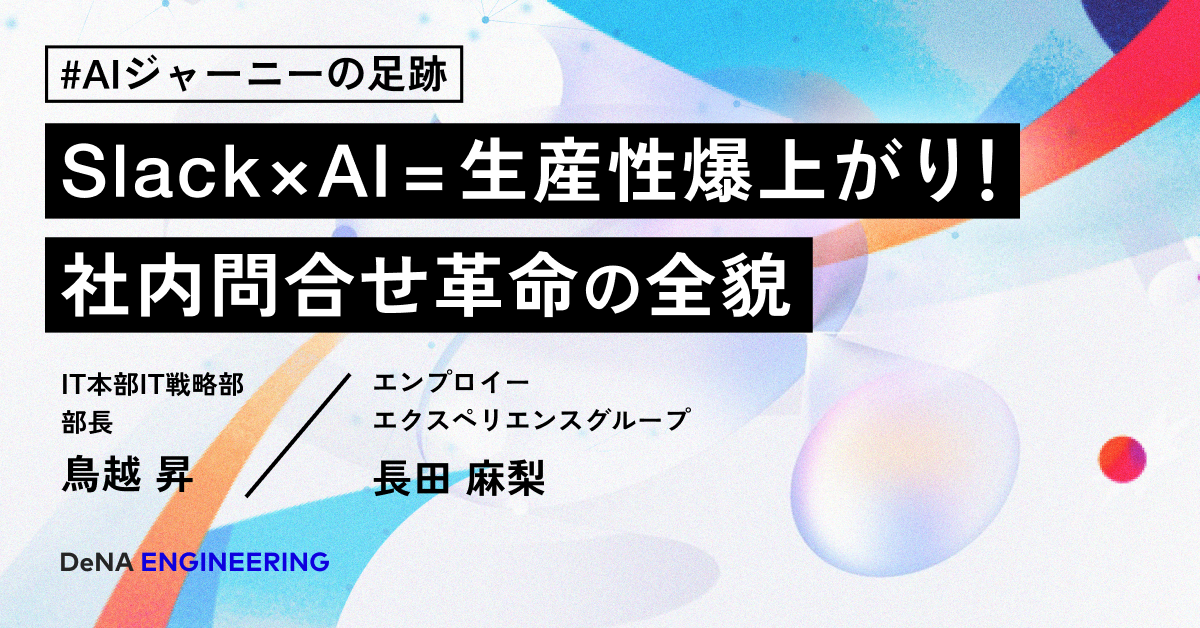

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。