はじめに
こんにちは、DeNAでAI研究開発エンジニアをしている鈴木( @x_ttyszk )です。2025年9月10日に渋谷オフィスでのオフライン開催とオンラインのハイブリッド形式で開催した「DeNA × AI Talks #2 - エンジニアのための、AIツール導入・活用最前線 -」( connpass )の開催レポートをお届けします。 本記事では、当日の発表資料と内容の要約をご紹介します。
DeNA × AI Talksについて
「DeNA × AI Talks」は、AI技術の最前線に触れ、実践的な知見を共有することを目的としたDeNA主催のトークイベントです。
DeNAでは今年2月にオンラインで DeNA × AI Day を開催しましたが、より定期的にAIに関する情報を発信し、参加者の皆さんと直接交流できる場を作りたいと考え、9月にこのイベントを立ち上げました。第1回の様子についてはこちらからご覧ください。
第2回目となる今回は、「エンジニアのための、AIツール導入・活用最前線」と題し、DeNAのエンジニアたちが実践する多岐にわたるAI活用事例が紹介されました。前回に続き渋谷オフィス・オンライン配信ともに多くの方にご参加いただき、活発な議論が交わされました。
動画
オンライン配信のアーカイブをYouTubeにて公開しています。
セッション
ここからは、当日の各セッションの内容をダイジェストでお届けします。
Introduction
登壇者:鈴木達哉
イベントの冒頭では、DeNAが掲げる「AIオールイン」戦略について紹介しました。

この戦略には3つの柱がありますが、1つ目が「AIによる全社生産性向上」です。AI活用により現状の3,000人体制を1,500人体制でも維持・成長させ、残りの1,500人を新規事業創出などにシフトすることを目標としています。本イベントではこの戦略の中で、エンジニアがどのように生産性を向上させているか具体的な事例を紹介しました。

社員個人や組織がAI活用を進めていくための取り組みのひとつとして、AI活用スキルを評価する独自指標 DARS(DeNA AI Readiness Score)を2025年8月末より導入しています。詳細はニュース記事『 全社のAIスキルを評価する指標「DeNA AI Readiness Score(DARS)」を導入開始』 をご覧ください。
PocochaのAI駆動開発推進体制
登壇者:松田悠吾
Pococha事業部バーティカルシステム部の松田より、 LIVEコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」 の開発においてAI活用をどのように推進しているのか、その体制と運用について紹介しました。
なお、本発表の内容についてはこちらもご覧ください。
開発プロセスの変遷とAI駆動開発の導入
Pocochaでは2022年のアジャイル開発導入に始まり、2023年にはScaled Agile Framework (SAFe)を導入し、最大10チームの体制を運用するなど組織を拡大してきました。そして2025年、AI駆動開発の導入に至りました。
AI駆動開発(AI-Driven Development)は、生成AIやLLMをプロダクトの企画、要件定義、設計、コーディング、テスト、リリースといった全フェーズで積極的に利用する開発手法です。これにより、開発サイクルの統合、開発スピードの向上、品質の統一、およびリリース時間の高速化を目指します 。AIの進化によって、従来は時間とコストがかかっていたプロダクト開発の前提が変わり、市場からのフィードバックを基にした高速な仮説検証が可能になりました 。
AI駆動開発の推進体制
AI駆動開発の推進にあたり、PocochaはTechチーム主導の段階的な導入と、生産性と学習のバランスを重視しました 。
-
Techチーム主導の推進: 全体戦略を策定する「AI駆動開発推進チーム」と、各技術チームから選出された「AI推進メンバー」からなる体制を構築しました。これにより、トップダウンとボトムアップを両立し、小さなコミュニティの力を最大化させることができています。
-
段階的な導入: LLM/生成AIツールの活用検証を各フェーズで進め、活用ガイドラインの整備や、AI CoP(Community of Practice)で知見を共有する環境を整えました。
-
生産性と学習のバランス: キャッチアップによる生産性の一時的な低下を抑えるため、即効性のあるAI活用を優先的に導入し、その余力でさらなる検証を進める方針です。
現在の取り組みと今後の展望
現在、Pocochaの全エンジニアが日常的にAIツール(Cursor、Claude Code、Gemini CLI、PR-Agent、MCP、Notebook LMなど)を活用しており、基本的なツール導入フェーズは完了しています 。今後は、個々のタスクにおける生産性向上に加え、プロダクトのアウトカム向上を目指します 。具体的には、ツール活用の深化(ルール化、プロンプトのテンプレート化、Agent化など)と、プロダクト開発プロセス全体の変革を進めていく方針です 。これにより、人間がより創造的な領域に注力し、ユーザーへの提供価値を最大化できる環境を目指します。
AIオールインの現場感、EMとしてどう思考し、どう動くか
登壇者:平子裕喜
DeSCヘルスケア製品開発統括部プロダクト開発部の平子より、ヘルスケアエンターテインメントアプリ kencom 開発チームが「AIオールイン」という経営方針を現場でどのように実現していったかについて紹介しました。
現状の成果と課題
kencom開発チームは、2024年秋と比較してすでにベロシティが2倍以上になりました。しかし、顧客に本質的な価値を届けるためにはスピードだけではなくクオリティを向上させる必要がありますし、エンジニアの個別最適だけでなく全体最適を考えるべきであるという課題があります 。
経営の号令を現場の物語に翻訳する
「AIオールイン」の方針が示された後、AI活用による生産性向上はkencom事業の最優先課題である「重いコスト構造の解消」を解決するための前提条件であることをチームに理解してもらいました。全社方針の「AIオールイン」はkencom開発の生存・成長戦略でもあります。「圧倒的な効率化」と「新たな価値創造」、「組織全体の活性化」というアウトカムを目指すことにしました。
ムーブメントを起こす
AI活用のムーブメントを起こすために、「ホットスポット」を作ることを提唱しました。まずは自身が「踊り手・フォロワー」となり個別に火をつけ、挙手制でワーキンググループを作って推進チーム化しました。これにより、内発的動機を焚きつけ、仲間を作りやすい場を作り、挑戦・学習・共有の文化を強化しました 。
攻めと守りの両立
DeNAでは、生成AIのリスクを管理しつつ、高速なPoCを可能にするガバナンスモデルを構築しています。具体的には、ツールトライアル申請とツール利用申請の二段階のワークフローがあり、試用中に法務やセキュリティの確認を並行して進めることで、安全に本格利用へ移行できる仕組みです。
バリューストリームと組織の全体最適
開発現場の生産性を低下させているのは、コーディングの遅さだけではなく、待ち時間や割り込み、手戻りといった「外的負荷」の積み重ねです。kencomチームはまず、エンジニア向けのAIツールを導入することで個人の効率を改善しました。しかし、次に目指すのはバリューストリーム全体の最適化です。外的負荷を削減し、チーム全員が設計や顧客価値の創出といった「本質的負荷」に集中できる環境を作ることが重要です。
AIソフトウェアエンジニアの「Devin」 はこの全体最適化の鍵になると考えています。Devinはソースコードや設計を誰でも理解できる「共有知」に変換し、知識の属人性を解消します。これにより、知識のハブとして外的負荷を吸収し、チーム全体の生産性を高めることができると考えています。
ヘルスケア事業全体の最適化
kencomチームはヘルスケア事業全体のAI活用を推進するAI CoEモデルにおいて、「先端ラボ」として位置づけられています。新しい領域やツールの開拓、実証、伝播を担う「ホットスポット」として、事業全体のイノベーションを牽引する役割を担っています。
PRDから始める、生きたドキュメントと実装への最短ルート
登壇者:黒木保
DeSCヘルスケア製品開発統括部プロダクト開発部の黒木より、ドキュメントをどのようにAIで作成し、活用していくかについて紹介しました。
「暗黙知」への依存
プロダクト開発では要求をコードに落とすまでにさまざまな情報を扱う必要がありますが、ドキュメントは部分的にしか作れておらず暗黙知化している状況でした。ドキュメントが作れていても質が不安定だったり、メンテナンスされていなかったりするために、結局実装した人に聞くか、コードを読むしかないという問題がありました。なぜできていなかったかというと、圧倒的にコストが高かったからです。
暗黙知に依存していたために、レビュー段階で実装の修正が必要になったり、担当者不在による開発停止リスクがあったり、AIへの指示に必要な「実装意図」「ドメイン知識」のドキュメントが足りなかったりという課題が出ていました。
新たなアプローチ
この課題を解決するため、人間にもAIにも理解可能な「実装設計図」をチームの共有知として確立させることにしました。具体的には、PRDからユーザーストーリーやドメインモデルなど各種ドキュメントをAIにより生成していく自動化プロセスを作成しました。

成果
この取り組みにより、以下のような成果が得られました 。
- 実装前の共有知化:実装前のドキュメント生成によって、一定の品質の共通認識が形成でき、仕様の認識齟齬が減少しました。
- AIの指示書としての活用:テストコードやDB設計のAIによる生成が行えるようになりました。
新しいペアプロ相手、AIとの向き合い方
登壇者:小野寺宏司
Pococha事業部バーティカルシステム部の小野寺より、AIをペアプロ相手として捉え活用していく方法について紹介しました。
なお、本発表の内容については ブログ記事「AIはペアプロ相手。開発者体験はこう変わった」 もご覧ください。
AIツールを使っていく中での気づき
昨今、生成AI関連のツールやキーワードが次々と登場していますが、とくにコンテキストを与える「Context Engineering」が重要になってきています。単にプロンプトを設計するだけでなく、コンテキストを共有し、意図を伝え、壁打ちを行うといった、対話を通じた開発です。この変化に伴い、AIコーディングエディターとのやりとりに対して、人と行う「ペアプログラミング」に似た感覚を持つようになってきました。
AIとのコーディングのコツ≒ペアプロのコツ?
ペアプロとは2人のプログラマが1台のマシンを操作してプログラミングを行う開発手法のことです。
次のようなペアプログラミングの効果は、AIとのコーディングにおいても得ることができます。
- 2つの脳を使うことによるより良い設計、抜け漏れの防止
- 発話・会話による思考整理
- コードの可読性、保守性の向上
- typoなどの軽微なミスを減らす
- 技術力の底上げと高い教育効果
- 開発環境の効率的な使い方やテクニックの共有
ただし、属人化の問題の軽減などAIとのペアプロでは難しい部分も存在します。
これからのペアプロ with AI
事前準備として、AIコーディングエディターが勝手に判断して動くことを制限し、作業内容をユーザーに確認するルールを設定します。
AIコーディングエディターとのやり取りの流れは以下のような形です。
- タスクの共有
- AIに作業内容・計画を立ててもらう
- 作業内容・計画の確認。対話による軌道修正
- 作業指示
- AIの作業内容の確認
最近効果を感じているプロンプトは「不明点、進めていくうえで確認すべきことがあったら都度ユーザーに質問してください。対話しながら進めましょう。また、作業中に問題があったら中断して都度ユーザーに確認してください」です。積極的にAIがコンテキストを埋めようとしてくれますし、承認した作業中に想定外の事象があったら中断してくれます。
また、AIを活用した上で人とのペアプロをすることも価値があります。AIとのペアプロでは実現できない属人化の問題の軽減といったことが期待できますし、プロンプトやコンテキストの与え方の知見を共有できます。
さいごに
渋谷オフィスの会場では懇親会も開催され、登壇者と参加者による議論や交流が活発に行われ大盛況のうちに終えることができました。
DeNA AI Talksは今後も1ヶ月に1回程度を目安に開催し続けていく予定ですので、引き続きよろしくお願いします。イベント情報は DeNA × AIのXアカウント @DeNAxAI_NEWS で発信しています。ぜひフォローお願いします。
次回開催予告
次回は10月14日(火)にDeNA × AI Talks #3 - 生成AIをコアとするプロダクト開発の舞台裏 - を開催します。
AIオールイン戦略の3つの柱の中の3番目「AI新規事業の創出・グロース」部分に焦点を当て、生成AIをコアとするプロダクトをテーマとしたイベントです。事業責任者やエンジニアが登壇し、事業戦略や開発知見、LLM基盤の工夫を紹介します。ご参加お待ちしております。
採用情報
DeNAでは現在、AIオールイン加速に向けて採用強化中です。興味のある方はこちらをご覧ください。
また、kencomのエンジニアチームではチーム紹介ページも開設していますので、ぜひご覧ください。






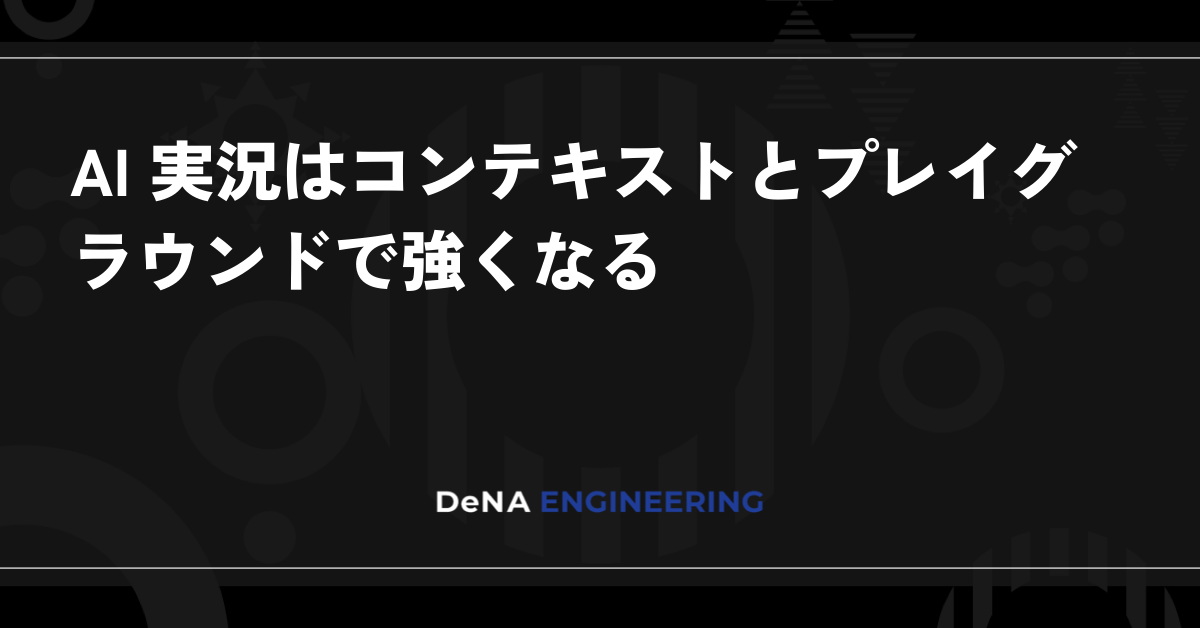
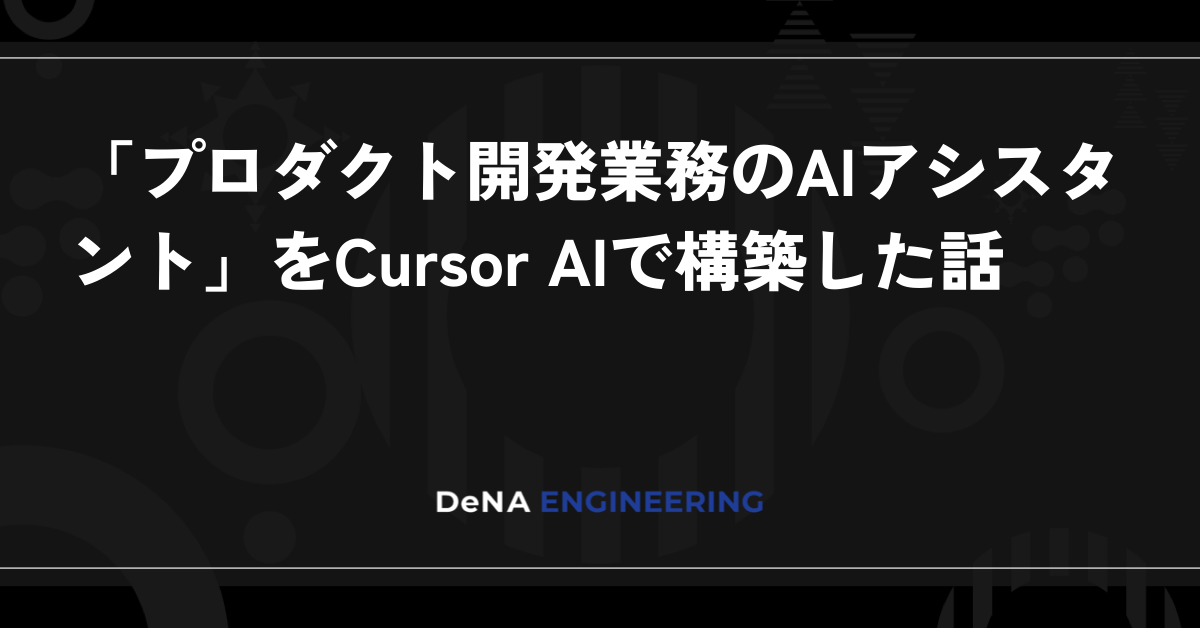
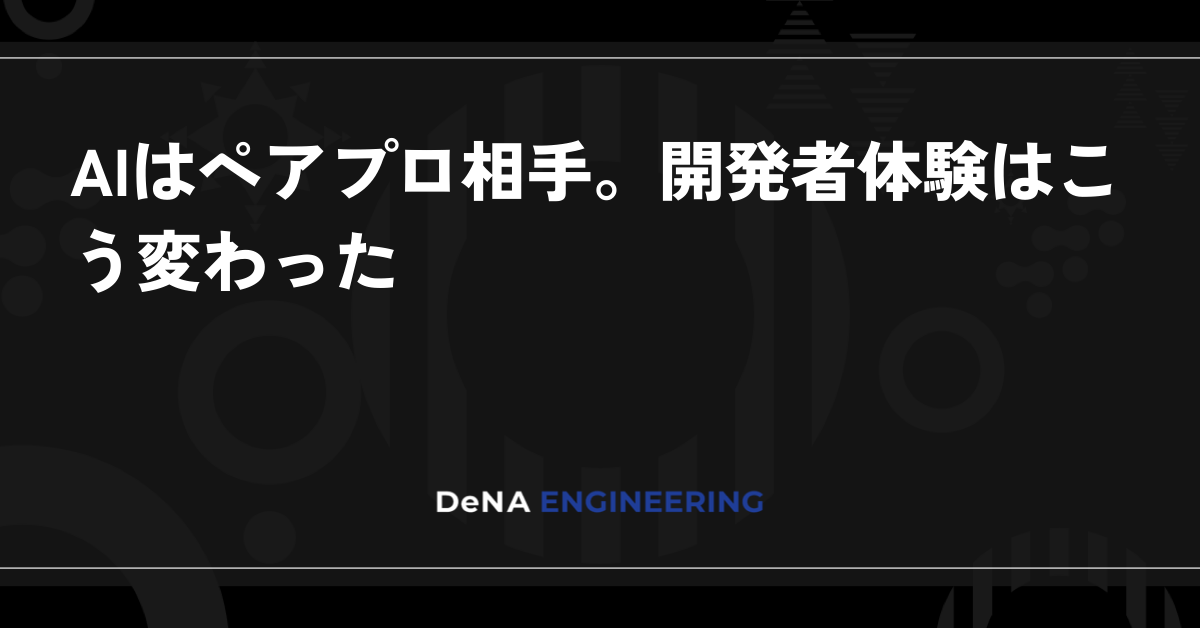

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。