はじめに
こんにちは。ヘルスケア事業本部ウェルビーイング事業部に所属している八森です。
2025 年 9 月 10 日、LINE ヤフーさん主催の勉強会『Creators Vision vol.2 〜生成 AI 時代における「私たち」の働き方〜』に参加しました!
本記事では、勉強会を通じて得られた学びや会場の雰囲気をお伝えするとともに、弊社から登壇したエンジニアとデザイナーによる発表内容についてもご紹介します。
イベント概要

今回のテーマは「生成 AI 時代における私たちの働き方」でした。AI の普及により業務の一部が置き換わる中で、職種ごとの責務や役割をどのように再定義するかを議論する場となりました。
イベントは以下の 3 つのセッションを通して進行しました。
- Session 1: 登壇発表
各職種における生成 AI の活用事例や、実際に置き換わりつつある業務プロセスを紹介しました。 - Session 2: パネルディスカッション
登壇内容を踏まえ、「生成 AI 時代において私たちの職種が担うべき責務とは何か?」をテーマに議論しました。 - Session 3: 懇親会
ディスカッションをもとに、参加者同士が今後の働き方について意見交換を行いました。
登壇発表
最初のセッションでは、各職種の登壇者から生成 AI を実務にどのように取り入れているかが紹介されました。
- 『Gemini で作る!新しいデザイン提案』 髙橋芽衣さん
- 『AI とともに歩んでいくデザイナーの役割の変化』 高橋柊蔵さん
- 『AI 駆動で 0→1 開発をやって見えた光と伸びしろ』 島岡秀知さん
- 『ソフトウェアエンジニアの生成 AI 活用と、これから』 泉水勇輝さん
各登壇者の発表資料は、主催の LINE ヤフーさんが公開している開催レポートにまとめられています。詳細はこちらをご覧ください。
本記事では、弊社から登壇した二人の発表を抜粋して紹介します。
Gemini で作る!新しいデザイン提案

髙橋さんからは、業務で Gemini のキャンバス機能を活用したプロトタイピングの事例 が紹介されました。
デザイナーとして、そしてチーム全体として、AI 導入前後でどのようにプロセスが変化したのか が語られました。
デザイナーの観点では、これまでは手作業で一画面ずつ構成していたため、細部の調整に意識が向き、プロトタイプの作成に時間を要することが多かったといいます。
一方で Gemini を活用することで、テキスト指示だけで全体を見渡しながら形にできるようになり、細部に入り込みすぎず議論用のプロトタイプを素早く準備できるようになったと振り返っていました。
チームの観点でも、これまでデザイナーが担っていた「アイデアのビジュアル化」を非デザイナーも試せるようになったことで、初期段階からの議論や合意形成がスムーズになったそうです。
結果として、アイデアや体験フローをより早い段階で可視化できるようになり、次のステップであるデザインのブラッシュアップや開発に多くの時間を割けるようになったとまとめられました。


AI 駆動で 0→1 開発をやって見えた光と伸びしろ

島岡さんからは、AI を活用した新規プロダクト開発の実践事例として、AI マッチングアプリ「fromm」の企画から MVP 構築までの取り組みが紹介されました。
短期間で MVP を実現することを目指し、各フェーズで AI を積極的に活用したプロセスが語られました。
リサーチの段階では、生成 AI やエージェントを用いて海外情報まで深く収集。
さらに、Bolt・Lovable・Dify などのツールを活用してモックを素早く作成し、少人数でもスピーディーに検証を回せた点が紹介されました。
開発フェーズでは、AI と協働しながら要件整理・コード生成・自動レビューを進行し、その結果、短期間で高品質な MVP を実現することができたと語られました。 一方で、AI レビューにはドメイン理解の難しさもあり、自動化だけに頼らない体制の工夫も求められたといいます。
最後に、個人としてもチームとしても、AI の進化をキャッチアップし、自ら試しながら学び続ける姿勢の大切さが語られました。


パネルディスカッション

続くセッションでは、登壇者同士によるパネルディスカッションが行われました。
テーマは「生成 AI 時代において私たちの職種が果たすべき責務とは何か?」で、登壇発表で紹介された具体的な事例をもとに、AI に置き換えられる業務と、人が担うべき役割をどのように切り分けるかが議論されました。
議論の中では、AI は単なる作業ツールではなく、共に検討しながら成果を形にしていくパートナーとして位置づけられました。
一方で、サービスの方向性や価値判断といった領域は、引き続き人間が担うべきものとして整理されました。
とくに、「何を実現したいのか」といった意図や、開発者自身のエゴや感性に基づく判断は、AI には代替が難しいとの意見も挙がりました。
そのため、こうした価値観や意図を明確に持ち、意思決定に責任を持つことが、人間に求められる重要な役割であるという点で共通認識が形成されました。
懇親会

懇親会では、登壇発表やパネルディスカッションの内容を踏まえ、職種を越えて活発な意見交換が行われました。
勉強会に参加してみて

職種を越えて、「生成 AI 時代における働き方」という共通のテーマに対して議論できたのがとても刺激的でした。 私はエンジニアとして参加しましたが、デザインの現場における生成 AI の活用は新鮮で、特に印象に残りました。
AI によって、アイデアを形にして検証するまでのスピードがこれまで以上に速くなったと感じています。
パネルディスカッションでも触れられていましたが、だからこそ「何をつくりたいのか」「なぜそれをつくるのか」といった意図を持って取り組むことの大切さを改めて実感しました。
参加者同士の交流でも、業務での実践やチームでの推進方法など、具体的なアイデアを数多く得られました。
これらの学びを、自分の領域での AI 活用や、より良いものづくりにどうつなげていけるかを探っていきたいと思います。
おわりに
今回のように、会社の垣根を越えて、それぞれの現場の知見を共有できたのはとても貴重な機会でした。
このような場を設けてくださった主催者の皆さま、そして参加者の皆さまとの交流にも感謝します。ありがとうございました。






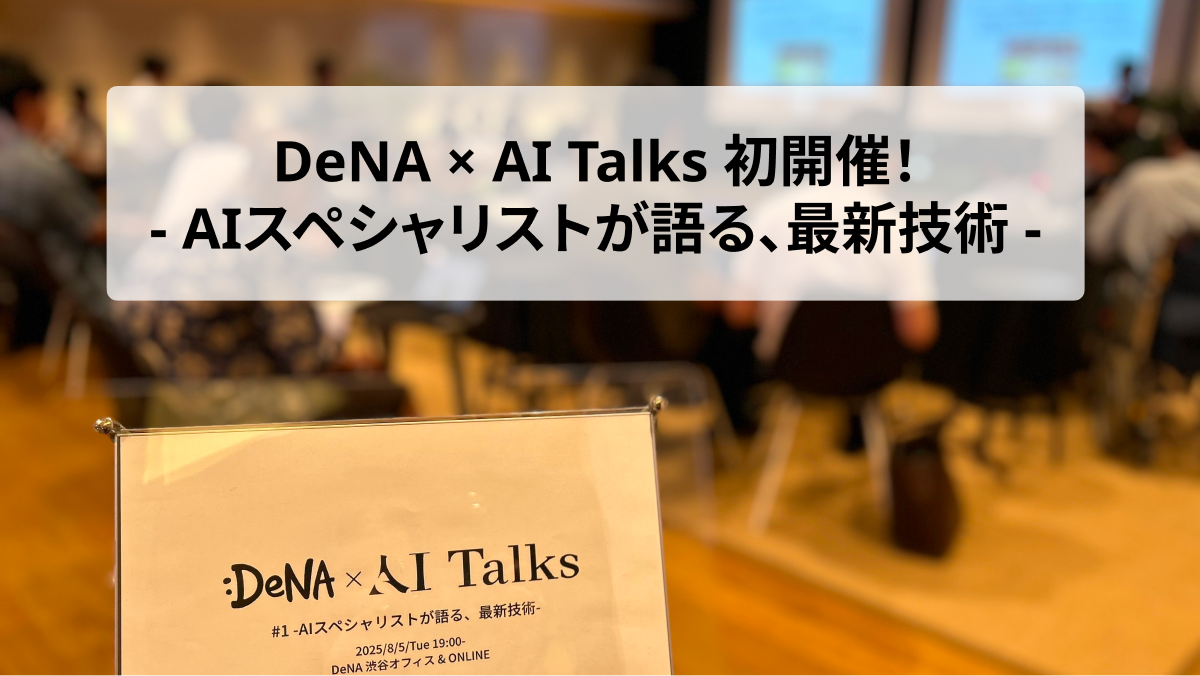



最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。