はじめに
皆さん、こんにちは。IT本部IT戦略部の部長の鳥越です。
私たちIT本部が全力で推進している「AIジャーニー」。
この取り組みは、単なるツールの導入ではなく、AIという新たなテクノロジーの力を活用して、私たち一人ひとりの働き方そのものを変革し、会社全体の未来を創っていくための壮大な航海です。
今回IT戦略部が担当するこの記事では、その重要な一歩となる、社内問合せのAI化について、ご紹介したいと思います。
日々の業務の中で、「この申請はどうすればいいんだっけ?」「PCのこの設定、誰に聞けばわかるかな?」といった疑問は、皆さんも一度は経験したことがあるはずです。実際、社内では毎日のように多くの問合せが寄せられています。
この「聞く」「待つ」といった時間を、もっと創造的で付加価値の高い仕事に使うことができたら…
その具体的な内容を、担当の長田からお話しします。
どうぞ、最後までお付き合いください。
DeNAの社内問合せの仕組み
こんにちは、IT戦略部エンプロイーエクスペリエンスグループの長田です。私は主に、全社の社内ITサポートの実施と、社内問合せの仕組み構築を担当しています。
DeNAでは、IT・総務・人事に関するすべての問合せを、社内問合せツールで一元的に受け付けています。
部門ごとに異なるシステムを利用するのではなく、共通の問合せツールを採用することで、社員は問合せ内容にかかわらず同じ操作方法・同じインターフェイスで相談できます。これにより、「ITの件はこのシステム、人事の件はあのシステム」といった使い分けの煩わしさがなく、一貫したユーザー体験を提供しています。
リプレイス前の仕組み
2021年から利用していた旧問合せツールでは、Webベースのチケット管理システムを採用していました。社員は専用のWebサイトにアクセスし、フォームに問合せ内容を入力してチケットを起票する仕組みでした。
問合せ担当者は、チケット管理画面で問合せ内容を確認し、メールやチケット内のコメント機能を使って回答を行っていました。問合せ者とのやり取りは主にメールベースで進行し、解決まで数日から極端なケースでは数週間を要することも珍しくありませんでした。
リプレイス前の課題:生産性向上への挑戦の始まり
旧社内問合せツールでは、まさに 「業務量を半分に、生産性を倍に」 という課題に直面していました。
増大する対応工数という現実
IT・総務・人事と多岐にわたる相談内容により、対応者の工数が増加の一途を辿っていました。これは、DeNAの事業拡大に伴い、社内からの問合せが複雑化・多様化していることの現れでもありました。
たとえば、以下のような幅広い領域の問合せが日々寄せられていました。
- ITに関する技術的な問合せ
- 総務での各種手続きに関する質問
- 人事制度や労務に関する相談
私たちは、これらすべての領域でAIによる回答を実施することで問合せ件数を減らし、対応工数を削減できないかと考えるようになりました。
ユーザー体験の変化への対応
また、社内でのメインコミュニケーションツールがSlackになってきており、従業員からSlackでの問合せを熱望する声が多く上がっていました。しかし、既存システムではこの要望に応えることが技術的に困難で、実現方法を模索していました。
旧問合せツールで直面したAI活用の課題と教訓
実は、旧問合せツールの時代から、私たちはAI活用の実験を始めていました。社内問合せ用のAIチャットボットを用意し、IT・総務・人事の各領域の問合せに対応できるよう構築しました。
しかし、期待に反してAIチャットボットはほとんど利用されることがありませんでした。社員は従来通りWebでの問合せ起票を行い、結果として人間が最初から対応するケースがほとんどでした。
この経験から、単にAI技術を導入するだけでは不十分で、社内問合せを行う中で、自然に利用できる仕組みづくりが重要であることを痛感しました。
新システム設計:AIファーストなアプローチ
新しい問合せシステムの設計では、「AIネイティブ」な問合せの実現を目指しました。とくに重視したのは、従業員が意識せずに問合せする際に、自然にAIを利用できる仕組みの構築です。
普段のコミュニケーションに利用しているSlackを問合せの入り口とすることで、 「まずAIに聞いて、分からなかったら人が対応する」 という流れをシームレスに実現しました。従業員にとっては、いつものSlackでの会話と同じ感覚で問合せができ、その背後でAIが自動的に回答を提供します。
重要なのは、AIが100%完璧ではないことを前提とした設計です。AIで解決できない問合せについては、ユーザーにストレスを与えることなく、シームレスに人による対応につなげる仕組みを構築しました。
AIを中心とした問合せフロー
新システムでは、AIが問合せ対応の「最前線」に立つ設計としました。
- 問合せ者はSlackで問合せを実施 - 慣れ親しんだツールでの直感的な操作
- AIが即座に回答を提示 - 数秒以内での一次回答により、この時点で問合せが完結することも

AIが回答できない場合には、問合せ担当者が対応します。
- AIの回答に満足できない場合は問合せチケットを起票 - シームレスなエスカレーション
- 専用チャンネルの自動作成 - 問合せ者と問合せ担当者の直接対話の場
- 問合せ担当者による対応 - ヒアリングと問題解決
- チケット管理ツールでの分析項目入力 - データドリブンな改善のための情報蓄積
- 問合せ内容からのケーススタディ自動生成 - 解決事例の構造化された知識化
- AI学習データへの追加 - 継続的な回答精度向上のサイクル

AIと人間の二人三脚によって、すべての問合せを解決します。
AI学習データの構築と継続的な知識拡充
AIの回答精度を高めるため、私たちは既存の情報資産と実際の問合せ対応の両方を学習データとして活用する仕組みを構築しました。
既存の社内情報資産の活用
まず、社内に蓄積された豊富な情報資産を学習データとして活用しました。
- 社内Wiki - IT技術情報、システム利用方法、トラブルシューティング手順、総務関連の各種手続きガイド、人事制度の詳細説明など
- 社内向け資料を格納したGoogleDrive - 各部門が作成した業務マニュアル、過去の研修資料や説明会資料、制度変更時の告知資料など
これらの既存資料を利用し、幅広い問合せに対応できる知識ベースを構築しました。
問合せ内容からのケーススタディ自動生成
さらに重要なのは、AIの知識にない問合せについて人が処理したやり取りを、AIに学習させる仕組みです。AIが回答できずに人間が対応した問合せのプロセス内容を学習データとして蓄積することで、人が専用の学習データを作成することなく、AIが回答できる範囲を継続的に広げています。
この仕組みにより、日々の業務の中で自然にAIの知識が拡充され、同様の問合せが次に来た際にはAIが適切に回答できるようになります。
成果と今後の展望:AIオールインの具体的な効果
定量的・定性的な成果
リプレイスから約3ヶ月が経過し、生産性向上の目標に向けて、具体的な成果が現れています。
ユーザー体験の劇的な向上
- AI回答による即時解決 - 数秒での一次回答により、多くの問合せがその場で完結
- Slackでの自然な問合せ体験 - 慣れ親しんだツールでの直感的な操作
- ユーザー満足度100%(問合せ者の65%がアンケート回答)
問合せ対応者の工数削減
- AI回答による問合せチケット数削減 - 人間が対応すべき案件の絞り込み(チケット件数20%減少)
- Slackでのリアルタイムやり取り - 従来の往復メールと比較して解決時間が大幅短縮(解決時間40%短縮)
今後の展望:さらなるAI活用の拡張
従業員が社内問合せする際に、AIの自然な利用は達成できました。次のステップとしては、AIのみで社内問合せを100%完了させることを目指しています。
現状、AIは質問に対する回答は得意ですが、依頼事項の処理はまだ人間が対応しています。たとえば、以下のような作業依頼については、AIが内容を理解しても実際の処理は人間が行う必要があります。
- アカウント作成や権限付与
- 各種設定変更などの作業依頼
内製システムの利点を活かし、社内システムとの連携を進めることで、最終的には作業依頼についてもAIが自動で処理を完結できることを目指しています。
社内からの反響
リリース後、予想以上に社内から好評の声をいただくことができました。これは、全従業員がAIを当たり前に使いこなすAIネイティブ化の第一歩として、非常に励みになる結果でした。
利用者からの声
問合せを行う社員からは、以下のようなコメントをいただいています。
Findout新しくなってめっちゃ体験が良い。AIが一次受けしてくれるのも助かる。
findoutを最近初めて使用しましたが、状況説明の文章をAIに要約してもらえて便利でした。(混乱しており文章を整えるのが難しかったので)
AIと人力のハイブリットにより、迅速かつ丁寧なご対応、ありがとうございました!引き続き、宜しくお願い致しますmm
この声は、まさに私たちが目指していたユーザー体験の向上が実現できていることを示しています。
対応者側の実感
一方、問合せ対応を行う私たち側の実感としては以下の通りです。
AIが最初に回答することによって、私たちへの基本的な質問が減りました。その結果、私たちは難易度が高い質問に集中できるようになり、より専門性を活かした対応に注力できています。
おわりに:AIジャーニーの一歩として
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した「社内問合せシステムのAI化」は、私たちの「AIジャーニー」における、まだ小さな一歩に過ぎません。
しかし、この一歩が、皆さん一人ひとりの貴重な時間を生み出し、本来集中すべき創造的な業務へとシフトさせていく、大きな原動力になると確信しています。私たちの目標である「業務量を半分に、生産性を倍に」という未来は、こうした一つ一つの変革の積み重ねによって、必ず実現できるはずです。
IT本部は、これからもテクノロジーの力を活用し、皆さんがより快適で、より生産的に働ける環境を全力でサポートします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。






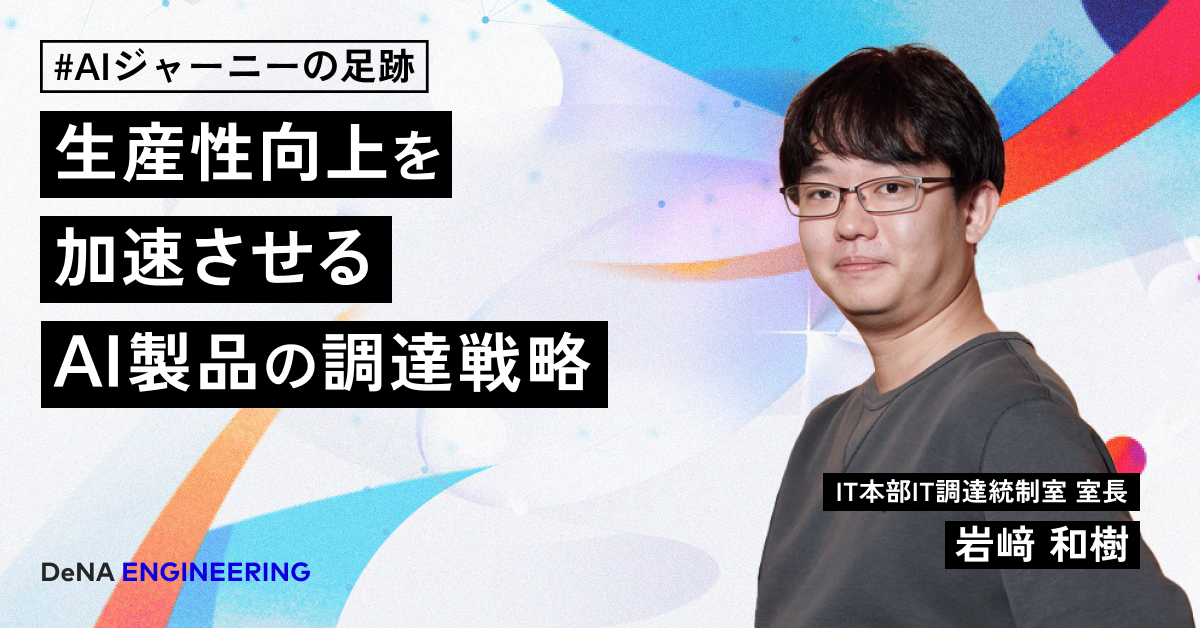
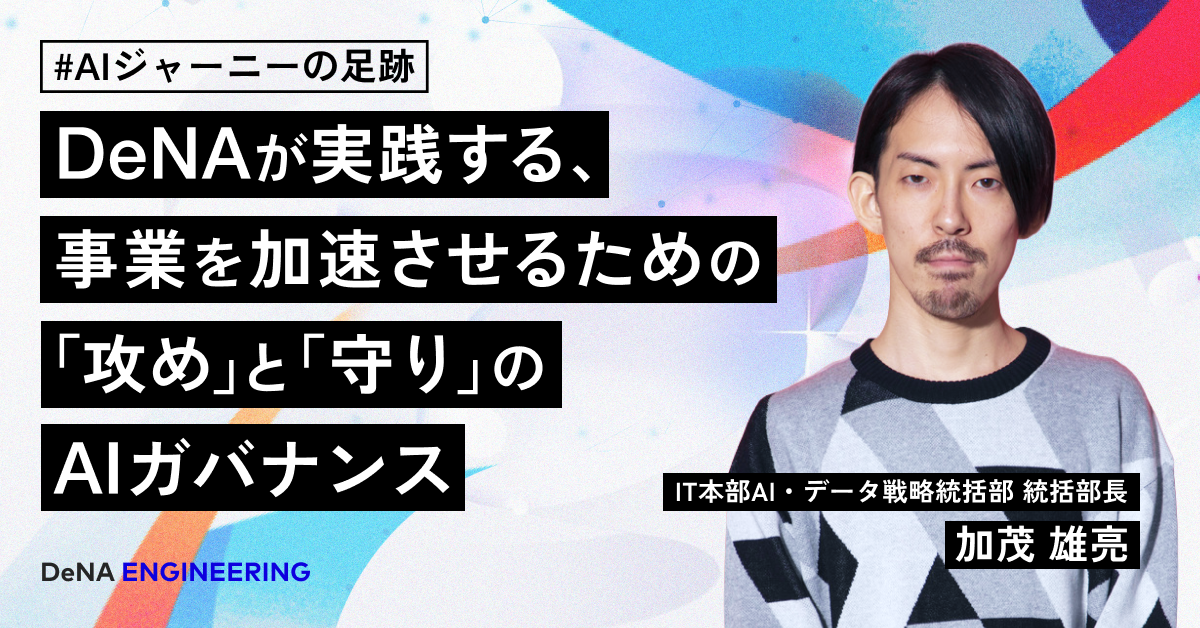
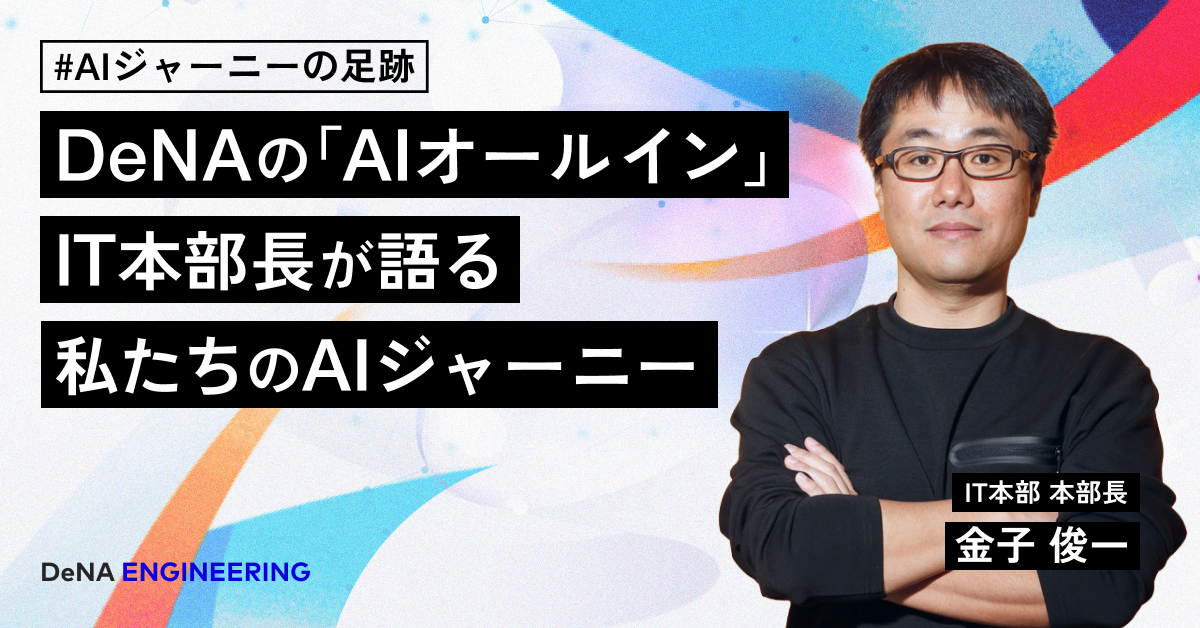

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。