IT本部IT調達統制室の岩崎です。
DeNAグループでは、全社的な生産性向上を目的として、AI製品の活用を推進しています。
私の所属するIT調達統制室は、全社で利用するIT製品(ソフトウェア、SaaS等)の調達やライセンス管理を実施し、全社のAI活用拡大を最前線で支える役割を担っています。
『 AIジャーニーの足跡 』連載の3回目となる今回は、AI製品の調達・運用管理を通して得た私たちの知見を、具体的な事例を交えてご紹介します。
1.DeNA全社導入したAI製品事例
DeNAグループでは、50種類を超えるAI製品が活用され、業務内容やニーズに応じて製品を使い分けています。
下記の表は利用者の多い代表的な製品を用途ごとにまとめたものです。
| 製品名 | 用途 | 主な機能 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Gemini for Google Workspace | 業務効率化 | ・メール要約、スプレッドシート整理、文章校正等多岐にわたる。 ・ミーティング要約、議事録作成 ・Gemini APP・NoteBook LM |
Google Workspace Enterpriseに付帯 |
| Atlassian Intelligence | 業務効率化 | Jira(プロジェクト管理)やConfluence(社内Wiki)の要約や検索等 | Jira Cloud及びConfluence Cloudに付帯 |
| Claude | 汎用 | ・対話型AI ・Claude Codeによるコーディング支援 ・APIによる各種利用 |
AWS BedrockやGCP VertexAI経由のAPIも利用中 |
| ChatGPT | 汎用 | ・対話型AI ・APIによる各種利用 |
|
| Cursor Business | 開発用 | コーディング支援 | |
| GitHub Copilot Business | 開発用 | コーディング支援 | |
| Gemini CLI | 開発用 | コーディング支援 | GCP VertexAIのGemini APIと組み合わせて利用 |
| Devin | 開発用 | 開発支援エージェント | |
| Adobe Firefly | デザイン用 | 画像生成 | Adobe Creative Cloudライセンスに付帯 |
上記以外にも、日々多くの新規AI製品に関する導入相談が寄せられており、新たな製品を積極的に活用する体制としています。
2.新規AI製品の選定における「3つのポイント」
導入相談における製品選定において、「ガバナンス・コスト・運用にかかる工数」 3つのポイントを重視しています。
これらはAI製品の選定を数多く行う中で徐々に明確になってきました。
1)ガバナンス:リスクを最小限に抑える管理体制
ガバナンスの観点では、利用規約の明確さと管理機能の充実度を重視します。
- 利用規約の明確さ
- 入力データの保存・利用ポリシーが明確に記載されているかをチェックします。特に、ユーザーが入力したデータがどのように扱われるか、ベンダー側での利用や保存ポリシーが明記されているかを確認します。
- 管理機能の充実度
- 管理者がユーザーや設定を一元管理できる機能があるかを確認します。
- ユーザー管理機能: 管理者によるユーザーの招待・追加が可能か、誰がどの製品を使っているかを把握できるか。
- 一括設定機能: 課金設定やオプトアウト設定など、管理者が一元的に設定を変更できるか。
- 管理者がユーザーや設定を一元管理できる機能があるかを確認します。
2)コスト:費用をコントロールする仕組み
コストの観点では予期しない費用の高額化を防止できるかを重視します。
- 料金の明確さ
- 料金定額プランはコスト見込みが立てやすいため、シンプルで管理がしやすいです。
- 一部製品の定額プランでは、高度モデルの利用には別料金が発生する場合があるため、注意が必要です。
- コスト管理機能の充実度
- 課金上限額の設定や事前のクレジット購入の可否を確認します。
- 従量課金制の場合、ユーザーの使い方で意図しない高額請求が発生する可能性があるため、コストモニタリング機能が充実していると安心です。
管理者のみ課金設定が変更できる・月ごとの上限金額を環境全体またはユーザー単位で設定できる機能が備わっています。
Cursor Businessのコスト管理画面
3)運用にかかる工数:管理の手間は最小限に
導入後の運用にかかる工数も重要な選定基準であり、利用ユーザーの管理がスムーズに行えるかを重視します。
- ユーザー追加削除の容易さ
- 製品の中には利用者ごとの電話番号認証が必要なツールもあります。追加の手間が多いことは管理工数の増加に繋がるため、実際の管理手順をしっかりと確認します。
- 自動化機能の充実度
- SSO(シングルサインオン)連携など、ユーザー管理の自動化が可能か確認します。管理の自動化は大幅な運用工数削減が期待できます。
3.導入後の運用・維持管理における工夫
どんな製品も、選定・導入して終わりではありません。AI製品は日々更新・進化しており、継続的な維持管理が必要です。
1) ライセンス管理の徹底
「誰が何を使っているかを正確に把握する」 ことは、ライセンス管理の最も重要なポイントです。
管理を徹底することで、セキュリティリスク発生時の注意喚起や、各種アップデート情報の周知、ライセンス費用の按分等をスムーズに実施できます。
DeNAでは資産管理システムにおいて製品ごとの利用者を管理しています。 資産管理システムでの表示例
下記はClaudeとCursor Businessの管理画面です。各製品ごとに利用者を管理しています。

2) ユーザーコミュニケーションの促進
一部のAI製品では利用者専用のSlackチャンネルを開設しています。
製品のアップデートやセキュリティ等に関する管理者からのお知らせだけでなく、利用者同士が製品についての情報交換やTips共有、製品利用に関する相談の場として機能しています。
こうした場を提供することで、管理者からのタイムリーな情報提供のほか、製品のさらなる利用促進に繋げています。
3) コスト・契約の管理
利用者数の増加にあわせ、プランのアップグレードやボリュームディスカウントの交渉を実施しています。
製品の中にはアカウント数によりビジネスプランやエンタープライズプランが利用可能なものがあり、アップグレードによる管理機能の強化やリクエスト上限数の緩和などメリットを受けられる場合があります。
一方で、特定の製品に依存することはロックインのリスクが高まるため、利用者拡大の際は製品のポータビリティ性(柔軟な製品乗り換えが可能か)を考慮して進めています。
4.AIの進化に追随するために意識していること
AIは急速に進化し、個別業務に特化したニッチなサービスも次々とリリースされています。
今後の予測が難しい状況の中で、調達において対応したこと・日々意識していることを紹介します。
1)有償製品の「トライアル」制度を開始
社内でのIT製品利用には利用申請やセキュリティチェックを必要としています。これらのチェックには平均して2週間程度が必要であり、すぐに製品を試すことが難しい状況でした。
新たな製品が次々とリリースされる現状において 「素早く試せないことは機会損失にあたる」 という仮説のもと、トライアル制度を開始。申請から1~2営業日程度で利用開始できる仕組みを構築しました。
トライアルでは「本番データを入れない、利用期限を厳格に管理する」といった一定の条件を設けることで、安全性を担保しつつ、各現場で最新製品を素早く試すニーズに応えています。
2)「素早い全社導入」を前提にした検討の実施
事前の情報収集において有用と判断した製品は、リリース前後に規約やセキュリティチェックを迅速に実施し、素早い全社導入を前提に検討を行っています。
有用な製品を素早く全社に届けることは、エンジニアリング組織としての重要なミッションだと捉えています。
Gemini CLIのリリース翌日に全社利用OKのアナウンスを実施した事例
3)社内の活発な会話から最新の情報をキャッチ
AIに関するカジュアルな情報交換の場としてSlackチャンネル「#ai-all-in」を開設し、自由な会話の場を提供しています。
全社従業員が自由に参加できるチャンネルとして運用し、現在は1,100人を超えるメンバーが参加しています。
AIに関する最新情報の投稿や製品をトライアルした感想など、日々活発なやり取りがされています。
このようなカジュアルな場を提供することは、従業員のAIへの興味関心やリテラシーの向上だけでなく、IT部門が最新のトレンドや現場のニーズを把握する上で非常に有用です。
#ai-all-inチャンネルでは活用方法紹介が多く投稿されています
おわりに
今回の記事では、AI製品の導入検討から導入・管理に至るまでの私たちの取り組みをご紹介しました。
AIは急速に進化しており、最適な製品を見極めるのは容易ではありません。
しかし、私たちは 「安全性を担保しつつ、素早く試して導入すること」 こそが、生産性向上につながる鍵だと考えています。
リスクを適切にコントロールしながら、コンパクトな導入を積み重ねることで、全社のAI活用を拡大し、業務効率化を推進していきます。
私は調達担当の立場ではありますが、これからも一人のエンジニアとして、社内の仲間や各ベンダーと協力・連携し、業務効率化に資するIT環境構築を進めます。






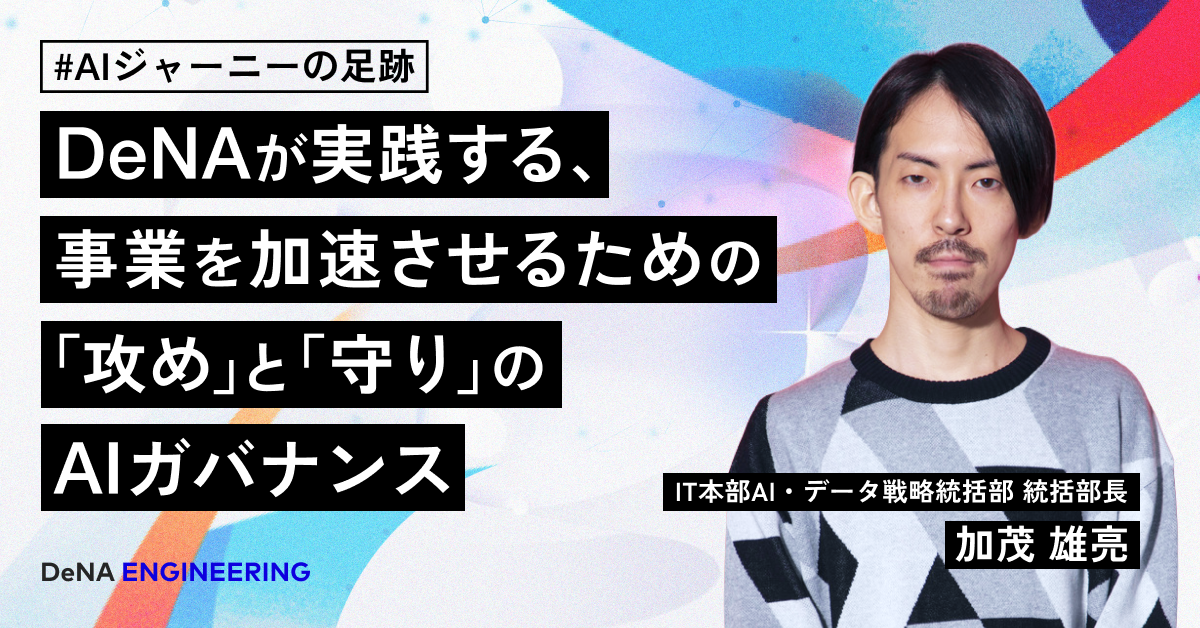
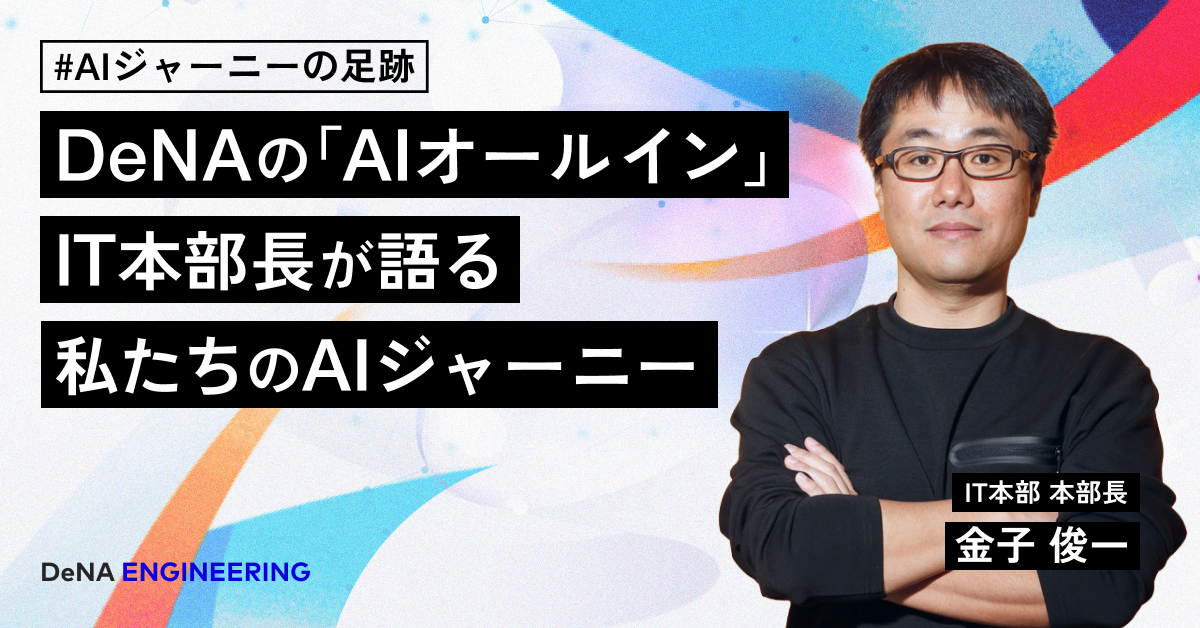
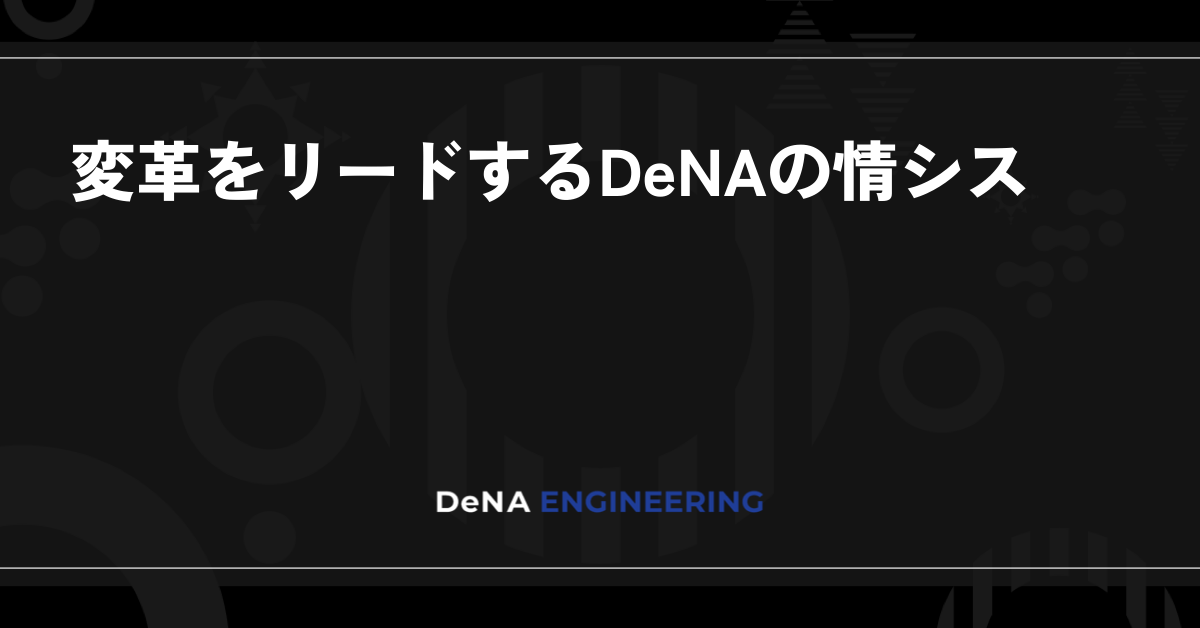

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。