はじめに:私たちの旅路が始まる
皆さん、こんにちは。IT本部 本部長の金子です。DeNAの技術戦略/センターオブエクセレンス(CoE)の統括をしています。
今日から始まるこの連載『 AIジャーニーの足跡 』では、DeNAが進めているAI戦略、そして壮大な変革の軌跡について、そのリアルな姿をお届けしていきたいと思います。初回は私の視点から、DeNAが「AIオールイン」という宣言を掲げた背景、その戦略の全体像、そして私たちが「AIジャーニー」と呼ぶ、この旅にかける想いについてお話しします。
IT本部について:AIジャーニーの推進ドライバー
本題に入る前に、IT本部について少し紹介させてください。DeNAのIT本部は、単なる社内IT部門ではありません。CoEとして、モノづくりの根幹をなすケイパビリティを全社横断で提供する組織です。

DeNAでは、各事業部に機能を分散するのではなく、横断組織/CoEとして集中させています。この横断組織があるからこそ、全社一丸となった大きな変革をスピーディに推進できる、これがDeNAの大きな強みです。この前提をご理解いただくと、これからの話がより立体的に見えてくるかと思います。
AIオールイン:なぜ今、全社で取り組むのか
「なぜ今、DeNAはこれほどまでにAIに注力しているのか?」
その理由はシンプルで、私たちはAIを「インターネットの登場以来の、巨大なパラダイムシフト」だと捉えているからです。この大きな波に乗り、変化の先頭に立つのか、それとも乗り遅れるのか。それが、DeNAがテックカンパニーとして今後も成長し続けられるかを左右する、重要な分水嶺だと考えています。
そこで掲げたのが「AIオールイン」です。これは単なるスローガンではありません。「全従業員がAIを使いこなすAIネイティブ化を含め、全員でこの変革に挑む」という、私たちの強い意志が込められています。
私たちはAIを使いこなしたうえで、生産性を倍にします。現在、DeNAの事業は約3,000人で運営していますが、それを半分の人員で、現状維持ではなくさらに成長させていきます。そして、残りの半分で、AIを核とした新規事業をやっていきます。
私たちのAI戦略
3つの柱
この壮大な旅、私たちが「AIジャーニー」と呼ぶこの取り組みは、3つの柱で構成されています。

-
全社の生産性向上: AIを使って社内のあらゆる業務を効率化し、従業員一人ひとりの生産性を劇的に高めます。
-
既存事業の競争力強化: ゲーム、スポーツ、ライブコミュニティ、ヘルスケア/メディカルなど、DeNAの既存事業の価値を、AIの力でさらに高めていきます。
-
AIによる新規事業の創出: AIを核とした、今までにない新しいサービスや事業を生み出していきます。
まず1つ目の 「全社の生産性向上」 は、私たちIT本部が先陣を切って進めている領域です。「業務量を半分に、生産性を倍に」という高い目標を掲げ、何よりも「成果」にこだわっています。現状はまだAIと人間は二人三脚の状態、AIの貢献度を日々数値化しながら改善を繰り返す、まさに泥臭いコンテキストエンジニアリングの渦中にあります。しかし、このリアルな挑戦から得られる知見こそが、未来の経営資源になると確信しています。
2つ目の 「既存事業の競争力強化」 は、AI/データエンジニアが各事業部に入り込み、事業部のメンバーとともにAIエキスパートチームを組成、シナジーを意識しながらさまざまな取り組みを進めています。AIとデータは事業の価値を最大化するための「テコ」であるという考えを根底に、事業が持つ本来の価値や解決すべき課題に対して、どのようなAI技術をどう適用すればそれに寄与できるか、という視点で取り組んでいます。特にゲームやスポーツの領域では、面白い取り組みが次々と生まれています。
そして3つ目の 「新規事業の創出」 では、DeNAのAIイノベーション事業本部が、AIを核とする「AIネイティブ」なプロダクトの開発に挑戦しています。既存プロダクトにAIツールを組み込む形ではなく、プロダクトの核となるサイクル自体にAIのフィードバックループを組み込み、それによってユーザー体験価値が継続的に高まっていくプロダクトを目指しています。
AIジャーニーを支える土台
これら3つの柱を支えるのは、私たちIT本部、そしてDeNAが長年培ってきた揺るぎない「土台」です。

多岐にわたる事業で蓄積された「多様なデータ資産」、GPUやLLM基盤を安定して構築する「強固な技術基盤」、そして何より「優秀なエンジニア」たち。この土台の上に、これまでのITガバナンスを拡張・適用したAIガバナンスを迅速に整備し、安全な環境で誰もがアクセルを踏めるようにしています。
人と環境へのアプローチ
全員でこの変革に挑むために、私たちは具体的なアプローチとして『人』と『環境』の変革も進めています。
『人』へのアプローチ
この挑戦は、一部の専門家だけでは成し遂げられません。だからこそ、全従業員がAIを当たり前に使いこなす「AIネイティブ」になるための環境づくりに、本気で投資しています。
私は「習うより慣れろ」の精神を大切にしています。特にエンジニアには、コーディングを支援するAIツールやAIエージェントを積極的に導入し、半ば強制的にでも(笑)、日常業務でAIに触れる機会を増やしています。
そして、これはエンジニアに限りませんが、「 DARS(DeNA AI Readiness Score) 」という、個々や組織のAI活用レベルを可視化する制度も始まりました。これは他人と比較するためのものではなく、自分自身の成長を実感し、次に何を学ぶべきかの道標にするためのものです。
幸い、DeNAには2016年からAI分野に挑戦してきた歴史があり、ノウハウを持った人材も多数います。そうした専門家たちが「AIエキスパートチーム」として、社内のあらゆる部門のAI活用を横断的に支援する体制も整っています。
私が最も期待しているのは「AIを使って、どうすればもっと面白いことができるか」と考えるマインドです。既存のやり方にとらわれない自由な発想で、AIを遊び倒すくらいの気持ちで、色々な業務の「ハック」に挑戦してほしいと願っています。
『環境』へのアプローチ
AIネイティブな作業環境への変革、これも、まさにIT本部が一丸となって進めていることです。日々の業務改善の先に見据えている、私たちの働き方の未来像についても少しお話しさせてください。それが 「DeNA AI Workspaces」構想 です。
これは、AIがまるで優秀な秘書やアシスタントのように、常に隣にいて業務をサポートしてくれる世界の実現を目指すものです。実現するには、ユーザーの意図を汲み取れるようAIエージェントを使い倒し、社内外の様々なツールをAPIで連携させるなど、エンジニアにとって非常に挑戦しがいのある技術的課題が山積しています。
また、この構想の恩恵を受けるのは、DeNA社内だけではありません。培った技術やノウハウは、新会社の 「DeNA AI Link」 を通じて、多くの企業の業務プロセスや働き方を変えるソリューションとしても提供していきたいと考えています。
おわりに:サステナブルな挑戦の旅へ
DeNAのAIへの挑戦は、一過性のイベントではありません。成果とチャレンジの好循環を生み出しながら、会社を次のステージへと押し上げる、サステナブルな取り組みです。
完成された綺麗な道はありません。むしろ、道なき道を自分たちで切り拓いていく、エキサイティングなフェーズです。だからこそ私たちは、変化を恐れず、この試行錯誤のプロセスそのものを楽しんで「面白い」と感じられる人と、ぜひ一緒にこの旅を続けたいと思っています。
さて、ここまで私の視点から「AIジャーニー」の全体像についてお話しさせていただきました。しかし、これは壮大な物語の、まだ序章に過ぎません。
AIネイティブ化に挑むためには、IT本部が持つ各機能の力が不可欠です。次回からは、IT本部の各部門を共に率いる部門長へバトンを繋ぎ、生々しい現場の声をお届けします。
さらに、未来のDeNAを担う新卒エンジニアたちが、社内を駆け巡り、IT本部が社内へ提供するAIツールやサービスが、ビジネスや開発の現場でどのように使われ、どんな化学反応を起こしているのかを、彼らの目線でレポートしてくれる予定です。
私たちの旅は始まったばかりです。ぜひ、これからのDeNAの旅にご期待ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。






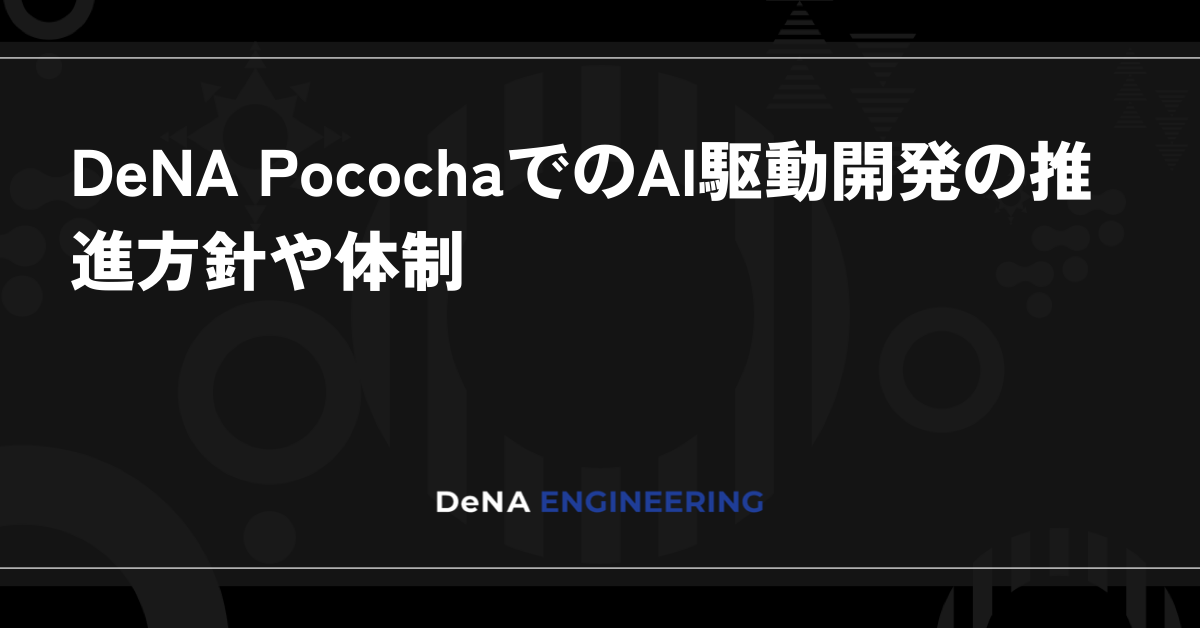
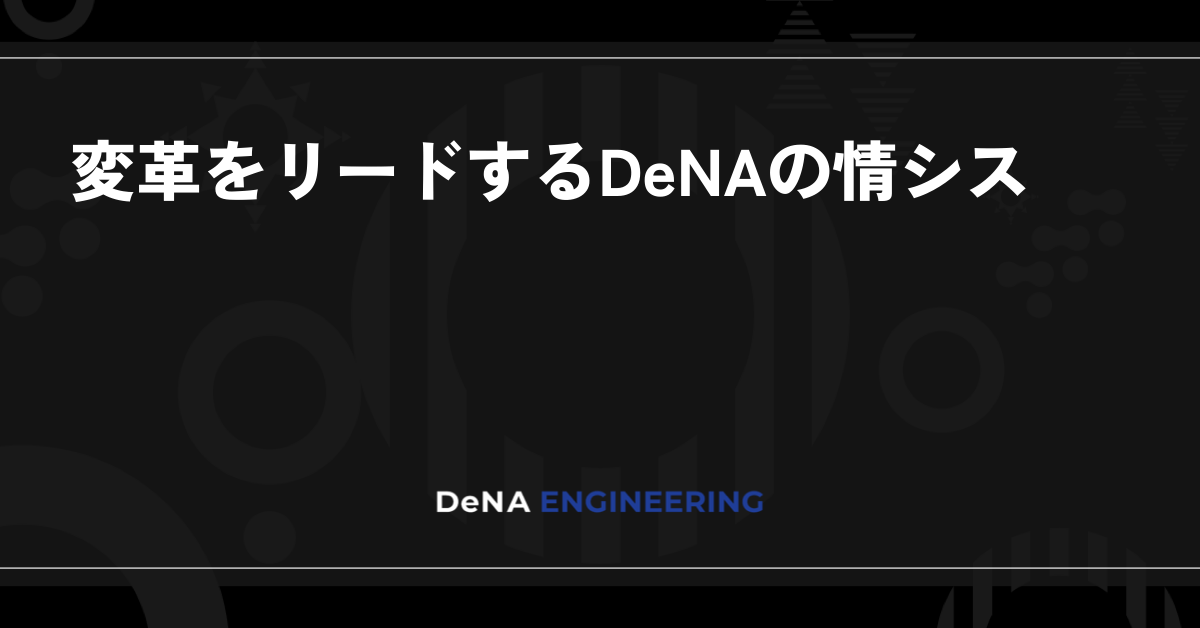
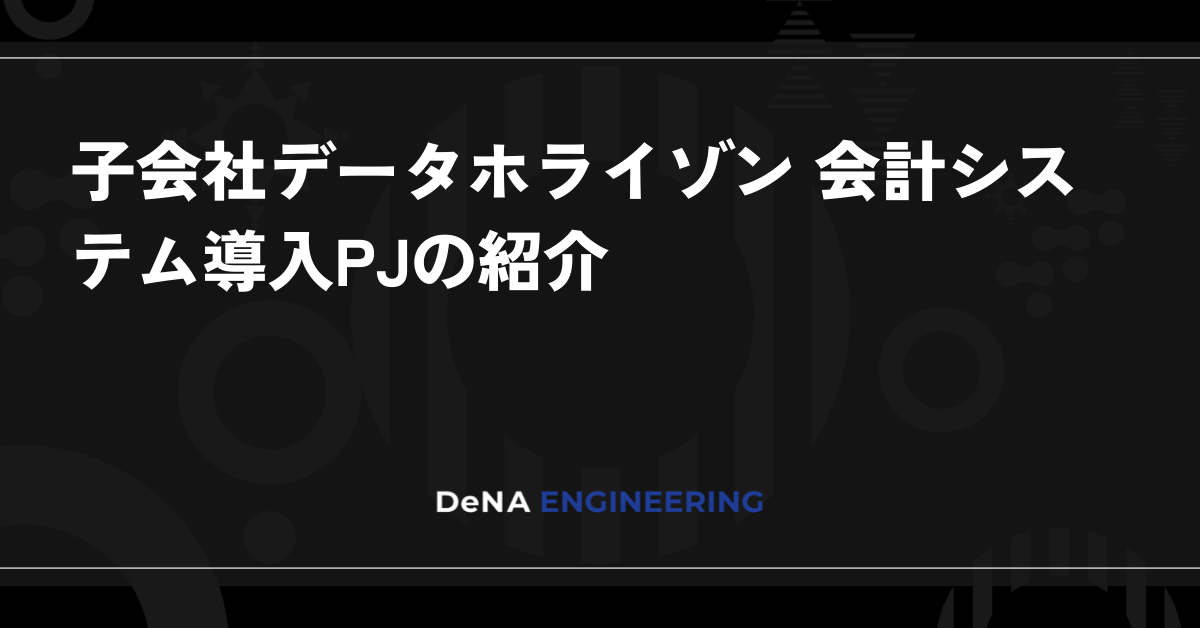

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。