はじめに
Pococha でプロダクト開発プロセスの改善をリードしている松田です。 Pocochaでは、2025年からAI駆動開発の導入に取り組んでいます。本記事では、AI駆動開発の導入経緯、推進体制、そして実際の実践事例について紹介したいと思います。
開発プロセスの変遷
Pocochaでは、これまで以下のような開発プロセスの改善を行ってきました
2022年:ウォーターフォール開発からの脱却として、アジャイル開発の導入・移行。XPやBDD、ATDD、アジャイルQAなどのプラクティスを1チームのパイロットチームの立ち上げから導入
2023年:サービスの成長に伴い組織もスケールし、Scaled Agile Framework(SAFe)を導入。最大10チームの開発チームを運用
2025年:AI駆動開発を導入開始
参考記事
AI駆動開発導入の経緯
現在、プロダクトに対してユーザーの需要がより複雑化、多様化しています。そんな不確実性が高い中で、ユーザーに価値を届けるためには、仮説検証を何度も繰り返す必要があります。
従来、プロダクト開発は時間とコストがかかるため、開発をする前に低コストで仮説検証を行うため、さまざまな手法が用いられてきました。 AIの進化により、従来に比べ、開発に時間とコストがかかるという前提が変わりつつあります。動くソフトウェアで、高速な仮説検証を行うことが現実的となってきています。 それにより、より解像度の高いフィードバックを市場から得ることができ、よりユーザーにとって価値の高いプロダクトを作りあげていけるようになります。
こういった、プロダクト開発の変化により、高速に仮説検証を繰り返す競合に対して、競争力で遅れをとるリスクがあります。 AI駆動開発の導入にフルコミットすることになりました。
AI駆動開発推進方針・体制
方針
AI駆動開発を導入していくにあたり、半年に一度開催しているPocochaのエンジニア全員参加のAll Handsで、「AI技術の進化と活用は避けては通れない重要なテーマであり、この変化をチャンスと捉え、戦略的に取り組んでいく」ということを共有しました。そして、導入していく方針として以下を発表しました。
- 段階的な導入
- Techチーム主導の推進
- 生産性と学習のバランス
それぞれについて詳しく説明します。
1. 段階的な導入
LLM/生成AI活用の検証
企画、仕様策定、設計、実装、検証、リリース、分析など、開発プロセスのフェーズごとに、LLM/生成AI活用のトライアルや検証を行っています。精度や効率性、実用性などを評価し、全体プロセスへの導入の優先順位を決めています。
活用に向けた土台の整備
エンジニアがLLM/生成AIを活用しやすいよう、手順書や利用ガイドラインなど、土台の整備をしています。 また、各自の学びを組織として最大化させるため、知見を共有できる環境の整備を行っています。PocochaにはCommunity of Practice(CoP)という制度があります。AI CoPを立ち上げ、AIに関する色々な学びを自由に共有できる場を作りました。Slackで情報の共有や週1回の定例を行なっています。
チームの成熟度に合わせた導入
チームによって、AIに関す知識や技術のキャッチアップ 度合いに差があったり、チーム内のコミュニケーションの密度の違いもあったりします。そのため、より実践的なフィードバックを集めていけるよう、チームの成熟度に合わせて導入やトライアルの実施を行っています。
2. Techチーム主導の推進
Pocochaでは以下の体制で、AI駆動開発の推進を行っています。 Pocochaでは、Server、iOS、Android、Webなど技術領域ごとのエンジニアが所属する組織体をTechチームと呼んでいます。
推進体制
-
AI駆動開発推進チーム:AI駆動開発導入や推進の全体戦略や戦術の検討や作成しています。また、ツールや環境、ガイドライン、ワークショップ、CoP運用等、推進しやすい環境を整備しています。全社からの情報の展開や他部署との連携も行っています。
-
AI推進メンバー:各Techチームや成熟度の高い開発チームそれぞれから1~2名選出。技術的な知見を活かした実践的なアプローチを行なっています。ツール使用可否やトライアルの実行など権限を一部委譲するなど、ボトムアップで活動しやすい体制にしています。
3. 生産性と学習のバランス
ユーザーに価値を届けるためには、生産性と学習のバランスが重要です。 トライアルやキャッチアップによる一時的な生産性低下を最小限に抑制しつつ導入をしていくことにしています。そのため、タスクの実行など、より即効性のある活用を優先的に導入しています。その結果、できた余力を活用し、さらなるトライアルや検証を行い、より大きな成果へと繋げていっています。
コミュニティで学びを最大化させる
こういった方針で進めていた中で、小さなコミュニティをいくつも作っていくことが重要であることに気づきました。Techチームや開発チーム、AIツールの活用度など、興味関心の近しい小さなコミュニティは、心理的安全性が高く、現場の推進力が高いため、各コミュニティの推進者にはできるかぎり権限を委譲し、コミュニティの自律性を尊重しています。 AI推進チームとしては、それぞれのコミュニティの活動を推奨し、良い事例があればワークショップ化したり、チームを跨いでモブプロを行ったりしており、コミュニティ間で各事例をパクり合いやすい環境づくりを意識しています。それにより、トップダウンとボトムアップの両立しやすい体制を作っています。
各コミュニティで以下のようなことを実践しており、そこでの実践例や学びについては、今後のブログで紹介をしていく予定です。
- チームでCursorを活用し、開発工数を6割削減
- PRDレビューやテスト項目作成にAgentを活用し、品質向上
今後の展望
ツール活用の深化
エンジニアの活用レベルを引き上げて、部内のエンジニアが全員すでに何かしらかのAI Agentを設計やコーディング、テストなど業務で活用していることを前提としたコミュニケーションへ移行をしていきます。
プロダクト開発プロセス全体の変革
Human In the loopをベースとしたプロダクト開発全体におけるAI駆動開発プロセスを定義し、移行をしていきます。 そのためには、企画段階からや、リリース後の検証など、非エンジニアのAI活用も推進していきます。開発アウトプットだけでなく、プロダクトの価値向上にもスコープを広げ、本質的に重要であるアウトカムの最大化に繋げていきます。
最後に
AIの進化はとても早く、3ヶ月後にはもう別のやり方をやっているかもしれません。ただAIがどれだけ進化をしたとしても、ユーザーへの提供価値を最大化するための手段であることには変わりません。AIの進化により、プロダクト開発の可能性はどんどん広がっているので、この変化を楽しんでいきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。本記事が、皆様のAI活用推進に少しでも参考になれば幸いです。






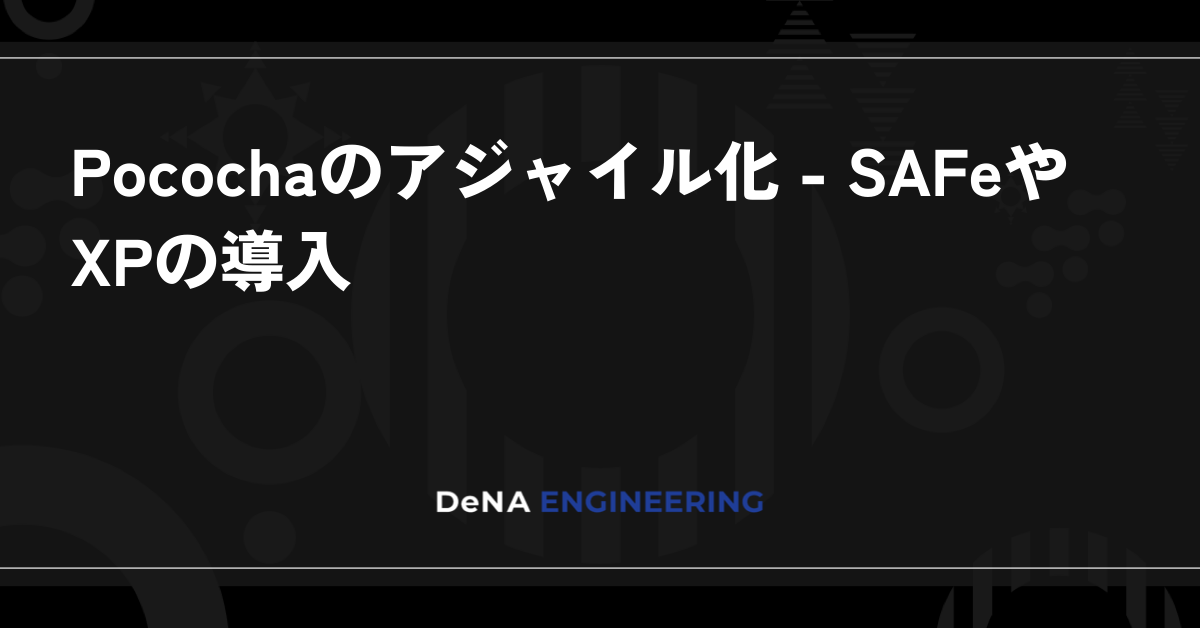
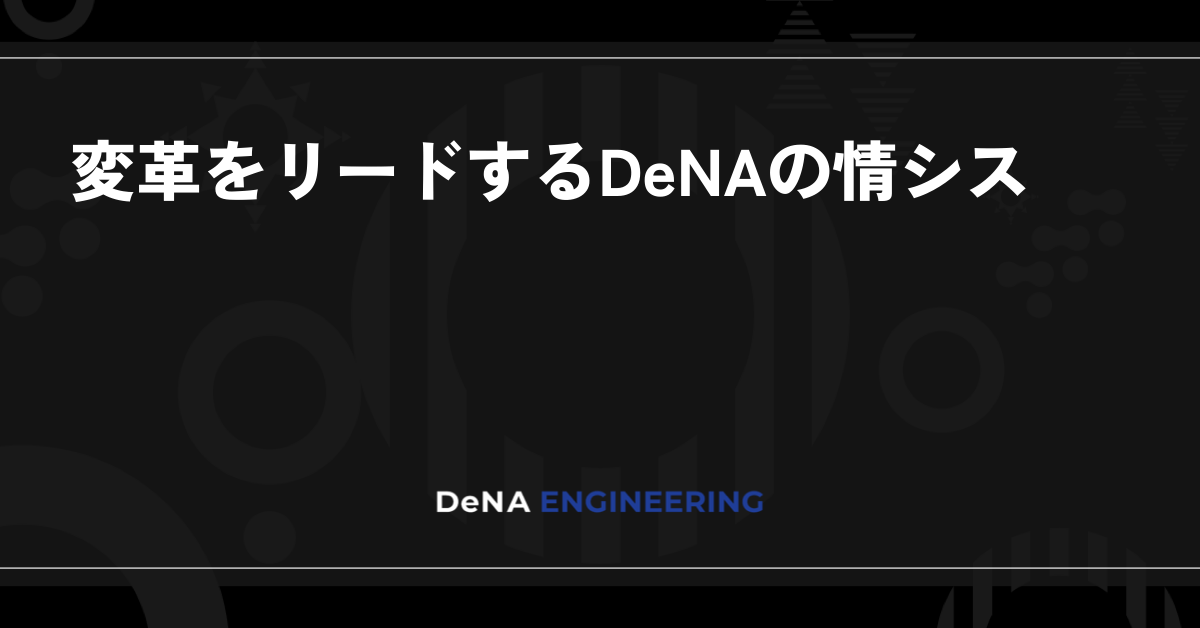
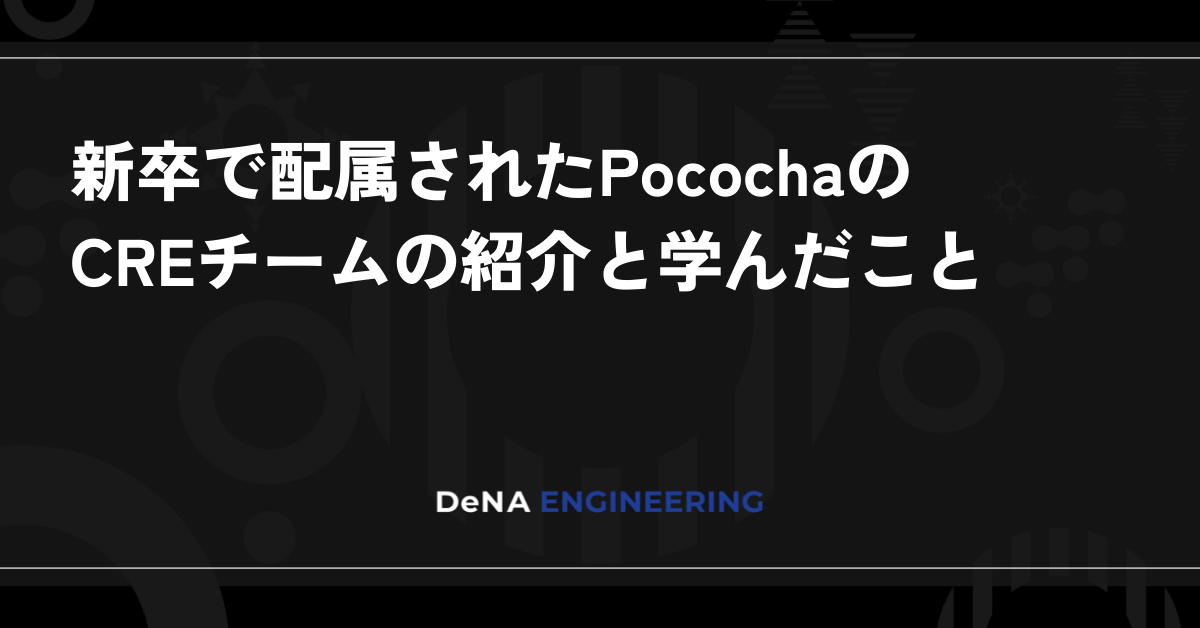

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
この記事をシェアしていただける方はこちらからお願いします。